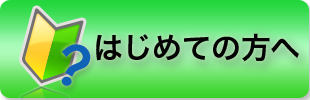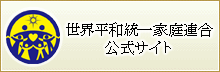はじめに
霊的集団「氏族協会」が、「祝福二世相談室」名で『救済論の問題点』(2008年11月1日初版)を出版しました。その内容は、禹明植集団に属する岡本達典氏の言説に基づくものです。
彼らは、『霊的集団「氏族協会」の誤りを正す!』(光言社、2006年1月25日出版、以下『誤りを正す』)に対して反論できず、06年4月12日に解散宣言し、しばらく潜伏していました。今回の出版目的は『誤りを正す』への反論にあります。しかしながら、『誤りを正す』の「原罪」と「血統」以外の本論23項目には一切触れることができず、反論していません。
『誤りを正す』は、文先生の御言と『原理講論』(以下、『講論』)は一致しているという視点から、原罪と血統を中心に「堕落論」を論じています。ところが岡本氏らは、御言と『講論』の「堕落論」が食い違うと言って批判しています。
今回の『救済論の問題点』は、不一致を主張するばかりか、『講論』は御言に対する「一つの解釈」(23頁)に過ぎないとまで述べます。彼らはプロテスタント神学の諸説をかき集め、「堕落論」批判に焦点を絞って、相変わらず「原罪の本質は自己中心の動機としての堕落性本性」(120頁)と繰り返し主張しているに過ぎません。
かつて岡本氏と論戦した際に、私たち3人(森、可知、竹内)は岡本言説を「原罪(淫行)隠しのサタン弁護論」(『続・文鮮明師の著作権』光言社、128頁、以下『著作権』)と喝破しましたが、今回の書はそれを裏づけています。
原罪とは、心の動機(原因)ではなく、「不倫関係を結んだ」結果をいうのです。文鮮明先生は次のように語っています。
「堕落は血統の不貞的動機から始まった事件でした。それゆえ堕落の結果が今日まで原罪として遺伝してきているのです。先生のときになって、堕落が愛によりもたらされた結果であるという事実を明らかにしたことは、驚くべきことです。これは歴史的背景を通して理論的に体系化されたものであり、否定できない内容です」(『祝福家庭と理想天国Ⅰ』436~437頁)
このように、堕落は「血統の不貞的動機」から始まった事件ですが、原罪とは「愛によりもたらされた結果」である「人間始祖が犯した霊的堕落と肉的堕落による血統的な罪」(『講論』121頁)を言うのです。自己中心(堕落性本性)は動機であって、原罪ではありません。文先生は次のように述べています。
「人類の願いは何かというと、堕落の仮面を脱ぐことです。堕落の仮面とは何でしょうか。血統が変わったというのです。血統の堕落とは何でしょうか。男性と女性が性関係を誤ったということです。誰を中心としてですか。サタンを中心としてです」(『天聖経』宇宙の根本、1906頁)
「男性と女性が性関係を誤った」とあるように、『講論』の原罪と性関係に関する理解は、文先生の御言と一致しています。
聖書に、アダムとエバが「善悪を知る木の実」を取って食べて堕落したとあります。この「木の実」は、精神的要素である“自己中心”でしょうか、それとも“エバの生殖器”でしょうか。原罪が何であるか、原点に立ち返って考えてみれば分かることです。文先生は「善悪の実は、エバの生殖器のことをいうのです」(『天聖経』宇宙の根本、1871頁)と、はっきり語っておられます。
ところがプロテスタント神学では、食べた「行為」よりも「戒め」を守らなかった動機(精神性)を心理分析し、心の中に原罪があるととらえます。岡本言説は、このプロテスタント神学の視点に立って「堕落論」批判を展開してきた、反対牧師をはじめとする“反対派の主張”の焼き直しにすぎません。
原罪の理解において、原因(動機)と結果を混同してはなりません。なぜなら、「不倫関係を結ぶこと」を原罪と思わず、軽視するようになるからです。もちろん自己中心の心の動機も問題です。私たちは自己犠牲の愛を実践し、心情革命をすべきです。
岡本言説の『救済論の問題点』が言わんとする結論は、統一教会の救済論は「いまだ不十分」であり、原罪や血統について「誤って信じられている部分」があると言うところにあります。彼らは、御言を綿密詳細に整理分析し、不十分な『講論』に取って代わって、新たに「成約原理」(?)が登場すべきであるとします。不遜にも、自分たちの言説が「成約原理」であると言いたいのでしょう。
一、『講論』について
(一)御言と『講論』の関係
文先生は『講論』を普遍的真理だとし、それを「先生がつくった御言の剣」「天的な宣言」「神様の心の中にある主流の憲法」(『著作権』145頁)と述べています。『講論』に対する先生の認識は、今も昔も一貫して変わっていません。
御言に対して、『講論』には保留にされている真理部分こそありますが、相互間に矛盾はなく一体です。真理であるのかないのかの判断は、真の父母である文先生が「どう言われているか」にあります。
(二)存在論的な「神概念」
『講論』は、最初に神(究極者)を存在論的に論じます。神学の神学たるゆえんは神をいかに認識しているかにあります。実際、神学の多くの問題点の解決は、神をいかに認識しているのかにかかっています。
パウル・ティリッヒ(AD1886~1965)は『組織神学』で、神概念を「存在自体」「存在の力」であるとし、統一原理と同様に存在論的にとらえています。そして、存在論的な神概念こそ「神論」における多くの問題と混乱を除去することができると述べています。また、この神観こそが「神を超自然の領域に幽閉している神学」より「宗教的である」と言います。「存在自体」としての神概念は、カント的な神認識、すなわち「神を道徳的規範理念(一存在)にするか、認識の基礎に信仰をおく不合理な信仰主義(fideism)によって超自然的な啓示を成立させる」という恣意的な神理解ではありません。
カント的原理は、究極的には神の自由と主権を保障するものの、「存在自体」としての神概念を見失うものでしかありません。ティリッヒは、存在に基盤を持たない一切の観念を斥けるのです。
現代社会は、既存の価値観が崩壊し、善悪の基準が分からず、社会秩序と家庭崩壊の危機に直面しています。この危機を救うために、神を存在論的にとらえ、キリスト教神学を再解釈し、体系化しようとしたところにティリッヒの功績があります。まさしくこの神概念の把握は、統一原理の神論を受容させるための“洗礼ヨハネ的使命”を担った神学であったと言えます。
(三)8つの分野でチャンピオン
『講論』の総序に「真理の一部分」とありますが、その一文をもって、普遍的真理の側面を見限ってはなりません。『講論』には、聖書の奥義を解明し、宗教や思想を統一する内容があります。
文先生は『平和神経』13番、16番のメッセージで、レバレンド・ムーンは、①神様、②サタン、③人間、④霊界、⑤イエス様、⑥聖書および各宗教の経書の核心内容、⑦人類歴史などを最もよく知り、⑧真の家庭の価値、これら8つの分野でチャンピオンであると述べています。
『講論』には、文先生がチャンピオンであると言われる内容があるのです。ところが岡本言説の『救済論の問題点』は、『講論』が聖句を多く引用していることから、「まるでキリスト教の“一つの派”にすぎないかのように見える」(26頁)と述べ、宗教を統一し得る内容がある点を見ようとしません。聖句を多く引用しているのは、キリスト者のために、『講論』が再臨主の神学思想であることを証しせんがためです。
文先生は、「堕落論」に対して次のように述べています。
「どこで天国と地獄が分かれるか調べてみましょう。空中ですか?どこですか?まさに皆様の生殖器です!深刻なことです。これが天地をひっくり返しました。この事実をだれが否定できますか?レバレンド・ムーンが発表した原理の本の堕落論に、説明がなされています。疑問に思えば神様に尋ねてごらんなさい。皆様としては夢にも想像できない内容と理論をもつて、体系立てておいたレバレンド・ムーンの原理の本に、だれしも反対することはできないのです」(『祝福家庭と理想天国Ⅰ』57頁)
ちなみに、文先生は、「『原理講論』という『原理』の本があるではないですか」(「ファミリー」09年1月号50頁)と語っておられ、原理の本とは『講論』を指しています。
ところが、岡本氏は「文先生の御言が絶対的基準である」(『95ヶ条+13の提題』57頁)と言いつつも、他方では「堕落論においても、完璧なものであると信じることは危険であり、むしろ盲目的行為であるといわざるを得ない」(岡本編「成約原理解説」1巻57頁)と述べます。これは二枚舌です。彼は御言に従わないだけでなく、それを否定しているのです。
(四)『講論』を修正できる主人公
岡本氏は、「真理の判断は『原理講論』と『文鮮明先生の御言』の、どちらに重点をおくべきか?」(岡本編『95ヶ条+13の提題』)と述べます。『救済論の問題点』でも「『原理講論』は、あくまでも文先生の『御言』の一つの『解釈』であり、『組織神学的解釈』なので、文先生の直接語られた『御言』のほうに、より宗教的権威がある」(23頁)とし、御言と『講論』の不一致を語ろうとします。
真理の判断基準は御言ですが、前述のように『講論』は「先生がつくった御言の剣」なのです。どちらも文先生の御言であり、「あれかこれか」との問題設定自体が誤りです。文先生の御言自体に対立や矛盾が内在するのではありません。人の主観が対立や矛盾を生み出すのです。
仮に『講論』の定義や解説に誤りがあるとしても、勝手に修正できません。修正すべき点があれば、それをするお方は文先生であり、それ以外の人ではないのです。
文先生は、「『原理講論』を修正することができる主人公は私しかいません。それを知っていますか」(『天聖経』宇宙の根本、1722頁)と明言しています。
また、2009年に入ってから、文先生は劉正玉先生に“修正する権限”を与えられましたが、そのような権限をもっておられるお方は文先生だけです。
(五)鍵を持つ人は?
『救済論の問題点』は、「教祖の語る内容(啓示)は、学問的に体系付けられたものではなく、時として『比喩』や『象徴』『暗示』といった、『詩的』で『難解』な言語による表現が多く含まれています」(20頁)とし、「合理的、かつ整合性のある解釈」のために「神学的作業」が必要であると述べます。そして、比喩や暗示で語られている部分を解くために「鍵」があると言います。その鍵を持つ人は、岡本氏自身であると言いたいのでしょう。しかし文先生は次のように語っています。
「愛する世界指導者の皆様、歴史上、いまだかってなかった位置で、人類をサタンの束縛から救い、天国へと導いてくれる鍵を持って来られるかたが、正に今、皆様の前に立っているレバレンド・ムーンです」(『平和神経』329頁)
さらに、自分が真理を解いたと大言壮語する人に対し、文先生は「自分たちが原理を解いたというのですか?わたしが解説してあげなければ、何の話か解くことができません。何の話かわからないのです」(「ファミリー」07年4月号44頁)と忠告しています。
(六)「真理の一部分」について
『講論』の総序に「真理の一部分」とあることから、岡本氏らは『救済論の問題点』で「『原理講論』が、再臨主である文先生の思想を組織神学化した最終的な教理書ではない」(27頁)と断言します。
劉孝元先生が、なぜ「真理の一部分」と記したのかを考えなければなりません。それは、不足面や部分性を指摘し、『講論』を批判することではありません。総序には、引き続き「深い真理の部分」の発表を待ち望むとあり、もし『講論』に表現上の誤りがあれば、それは弟子(著者)の責任だというのです。
それは、文先生が書いたものを批判すれば天法に引っかかり、批判者はそれ相応の蕩減を受けるからです。それで著者が書いたとし、著者が責任を持つというのです。それは批判者にとっての救いです。その配慮を、批判者たちは知らなければなりません。
「真理の一部分」の表現は、『講論』に「保留にされている真理」があることを意味します。その保留部分と『講論』が一体となって、完全な真理(原理本体論)となるのです。
二、「原罪」に関する神学的諸問題
(一)原罪を探求する意義
原罪とは何か? そのとらえ方の違いが、救済観の相違となります。その意味で、原罪論は教義の核心と言えます。
『講論』は、天使長と人間始祖の「不倫な関係」(淫行)が原罪とします。この原罪論に対して、日本共産党は「珍論」と嘲笑し、浅見定雄氏は祝福結婚による血統転換は「血分け」と批判し、飯干晃一氏は「人類の始祖がサタンと性交したと強弁するところから、統一教会の邪悪がはじまる」とします。
岡本氏らは、この反対派の「堕落論」攻撃の戦略から、何らかの影響を受けたのでしょう。それで、プロテスタント神学の原罪論(自己中心)が正しいと強弁し、「堕落論」を批判するのです。
私たちは、これらの一切の批判を放置せず、真摯に応答し、何が真理であるのかを鮮明にしなければなりません。それは、現代人がフリーセックスの奴隷となり、背倫の渦の中に溺れて家庭を崩壊させ、地獄に直行している現実があるからです。人間社会のサタン的な淫乱の弊害を一掃し、彼らを救済しなければなりません。
罪の根が何であるかを究明し、それを清算しなければなりません。そこに「原罪とは何か?」を解明する目的があります。
カール・バルト(AD1886~1966)は牧師でありながら社会民主党に入党しました。しかしその後、バルトは、社会民主党が聖書にある“罪認識”に欠けていることに気づきました。文先生も、悪や罪の源を解明した堕落論の重要性を次のように語っています。
「これからこの世界問題を解決して、人類の道徳問題をすべて解消させるためには、堕落論がなくてはならないのです。堕落論なくしては人間の問題が是正されないのです」(『天聖経』成約人への道、1615頁)
(二)「原罪論」と血統に対する争点
1 日本共産党の見解
日本共産党は『講論』を珍無類な聖書解釈とし、堕落論を批判します。
「統一協会のように、蛇の正体が天使であり、姦淫によって堕落したといった珍論は、世界のどんなキリスト教の異端派にもない解釈であり、聖書そのものにまったく根拠をもたないつくり話にすぎない。『原理講論』を、まともなキリスト教徒が一笑に付して、相手にしないのももっともである」(『原理運動と勝共連合』123頁)
彼らは、「姦淫によって堕落した」との主張は、「世界のどんなキリスト教の異端派にもない解釈」であると言うのです。共産党の言動が常にそうであるように、これは戦略的な文章に他なりません。
2 キリスト教の「原罪観」と「原罪の遺伝」について
自由主義神学は、搾取や抑圧や差別、それに非人間的・反民主主義的な独裁体制などを罪と見て、体制改革を主張します。このような社会説は、共産主義の革命運動の戦略戦術に利用されます。体制が罪ではなく、罪がそのような体制をつくり出すのです。自由主義神学は社会の諸悪の根源となった原罪に対して無関心です。
原罪という言葉を最初に使ったのはアウグスティヌス(AD354~430)です。彼は次のように考えました。
「アダムの罪は、人類の末端にまで及んでいる。子孫は、性を通して生まれるがゆえに、性は二重の意味において罪の根源となっている。すなわち、一人ひとりの人間が、性を通して生まれたということが、すでに罪に満ちていたし、罪を犯す傾向性も、実は先天的な弱さとして、受けつがれてきている」(W・E・ホーダーン著『現代キリスト教神学入門』46頁)
プロテスタント神学は、人間の病の根源を「精神的なもの」(貪欲、傲慢、自己中心)ととらえます。しかしそれがどう始まり、どのように伝えられるのかという点になると、ホーダーンは「アウグスティヌスの、アダムとその罪の遺伝についての教義を学ぶ必要性がある」(同)と指摘し、「罪の精神性とでもいうべきものが、生物的なものへと変わっていったというように考えられる。罪の心理的分析と、その生物的遺伝的な側面の、どちらに軍配をあげ、どう調和するかということは、容易なわざではない」(同)と述べます。
このように、どう調和するのかは容易ではありません。原罪を“精神性”ととらえるか、“生物的遺伝的”ととらえるのかといった問題から、キリスト教神学は二分され、一方をとり他方を否定する問題が起こりました。プロテスタントは、信仰義認論の立場から生物的遺伝説を退け、カトリックは、マリアの「無原罪の御宿り」の教義の中にそれを見るのです。
(三)カトリックの「原罪論」
1 カトリックの「汚れなき懐胎」説
ローマ教皇庁立大学のカーリ・E・ビョレセン教授は、論文「カトリック神学におけるマリア」(『マリアとは誰だったのか』)で次のように述べます。
「汚れなき懐胎という考え方の前提をなしているのは、原罪は父親の生殖行為からくるというアウグスティヌスの教説である。このため、理性的な魂が吹き込まれる瞬間にインフェクチオ・カルニス〔胎児感染〕が起こる。……キリストは、人間化の際の聖霊の働きにより、この感染から免れる……。男性中心主義の生物学によれば、原罪は、能動的な役割をはたす父親によってもっぱら伝えられる」(126頁)
この「原罪は父親の生殖行為からくる」との学説は、統一原理の原罪理解と同じです。また、この原罪論と「汚れなき懐胎」説は、イエスがなぜ無原罪として誕生されたのかという重要な神学問題に関連します。
2 中世の「スコラ神学」
次に、スコラ哲学者らのマリア論における原罪観の諸説を見てみましょう。
「8世紀(ダマスクスのヨアンネス)より、マリアはその母性のゆえに原罪の汚れから清められたとするのが適切だとみなされるようになる。主要なスコラ哲学者たちは、マリアは人間として普遍の懐胎により胎児感染を引き起こしたが、つづいて償いの介入により聖化されたのだという見解をいだいていた。この介入は2段階で成就される。まず、母胎内で、――聖化の瞬間……肝心なのは、どのようなものであろうとアクチュアルな罪すべてからの解放であった。これらの教父たちによれば、エレミヤやバプテスマのヨハネもイン・ウテロ〔子宮内〕で聖別されているという。もっともただ神の恩寵を失うような大罪からだけではあるが(エレミヤ一・5〔私はあなたを母の胎内につくる前から……〕/ルカ一・15)。第2段階とは、マリアがキリスト懐胎の瞬間に聖別された(ルカ一・35)ことだという。この瞬間、彼女から原罪は完全に駆逐された」(ビョレセン著、同)
カトリックの原罪理解は、「性質」(堕落性本性)とは違って、『講論』と同じです。また、『講論』の「原罪の遺伝」(サタンの血統)という説を「人間として普遍の懐胎により胎児感染を引き起こした」の個所に見ることができます。
さらに、「アクチュアルな罪すべてからの解放」「イン・ウテロ〔子宮内〕で聖別されている」との説を、「タマルの胎中復帰」の原理の中に見るのです。
文先生は「タマルについて研究すれば、原理のすべてが分かる」(『祝福家庭と理想天国Ⅱ』77頁)と語っていますが、岡本言説のようなプロテスタント神学を代弁する見解では、「原罪の清算」と深く関係する「タマルの胎中復帰」が意味する「原理」を解明することはできません。せいぜい「種」は心情で、「胎内」は聖霊であると述べ、客観的存在を認識しない主観的観念論の見解でとどまります。そして、「胎児感染」や「子宮内」聖別、「種」を説くのは生物学的な「血分け」理論と言って揶揄するぐらいの程度でしょう。
ビョレセンは、カトリック神学の「インフェクチオ・カルニス〔胎児感染〕に先だつ介入という考えは、マリアの懐胎の祝日と結びついて生れたものでもある。これは11世紀末、英国で普及し、12世紀にはヨーロッパ全土に広がった」(同)と述べます。
この原罪論は、「生殖」すなわち汚れという観念が前提となっています。
(四)大木英夫氏の原罪解説
「原罪という語はアウグスティヌスによって用いられた概念であるが……本来の意味は〈遺伝的な罪〉〈相続された罪〉であって、堕罪したアダムとエバから生殖作用を媒介として代々相続された罪をいうのである」(『キリスト教組織神学事典』268頁)
これは統一原理の性関係による血統的、遺伝的な罪という原罪論それ自体の聖書の解釈と言えます。堕落論は、共産党が言うような、まともなキリスト者が相手にしない、世界のどんなキリスト教の異端派にもない「珍無類の聖書解釈」ではありません。
三、浅見定雄氏の批判と『救済論の問題点』の接点
(一)浅見氏の堕落論批判
浅見定雄氏(日本基督教団)は、次のように堕落論を批判します。
「人間の『原罪』が遺伝しているという説は伝統的キリスト教にも確かにある。しかしここで私が指摘しているのは、エバとルーシェル、エバとアダムとの性的不倫という『行為の結果』が遺伝していると主張する『原理講論』の珍論のことである」(浅見定雄著『統一協会=原理運動』134頁)
浅見氏は、堕落論を「珍論」と批判しますが、その理由については明言を避け、あえて述べようとしません。脱会説得を効果的に行い続けるための作戦なのでしょう。
岡本言説の『救済論の問題点』は、浅見氏が黙した“理由付け”を具体的に述べ、堕落論を批判します。これによって、反対牧師らが統一教会信者を脱会説得するにあたって、堕落論をどのように批判しているのかが明瞭になります。
(二)生物学的な「血統」概念
浅見氏が「珍論」と指摘するのは、原罪がいかに始まり、それがいかに遺伝するのかという堕落論の教義についてです。それは、「原罪」と「遺伝法則」の関係に対するプロテスタント神学的な概念から来る疑念です。
1 「精子と卵子」と血統
文鮮明先生は精子と卵子について次のように述べます。
「皆さんが父母から受け継いだ命は、父の精子と母の卵子を受け継いだところから出発したのです。その卵子と精子が一つとなったところに、愛によって根が生まれて発生したのが、皆さんの子女です」(「ファミリー」07年3月号7頁)
このように、父母から子女への生命の連結、すなわち「血統」に対し、それは愛を中心として精子と卵子が一つとなることから出発したと、生物学的に述べています。
ただし精子と卵子の生物学的次元の指摘だけでなく、さらに深く考察され、「愛によって根が生まれて発生した」と愛を強調しています。神様の血統に連結するか、サタンの血統に連結するかという問題は、この愛を認識しなければなりません。真の愛か、利己的愛か。科学はそこまで論じませんが、これは哲学や神学の分野です。
岡本言説である『救済論の問題点』は、「御言の示す血統は心情の関係」(128頁)であると述べ、「『精子と卵子』といった『生物学的物質』即ち『生物学的DNA』を媒介としたものでない」(同)と断定します。彼らはここでも御言を否定します。
ちなみに、卵子の発見ついてビョレセン教授は次のように述べています。
「カール・エルンスト・リター・フォン・ベーアによる哺乳類の卵子の発見(1827年)により、男性中心主義的に女性を理解しようとするキリスト論の前提は崩れる。ここで父と母との機能が同等のものであるとしてみられる」ようになったのです(『マリアとは誰だったのか』122頁)。このように「卵子の発見」は、女性の復権にも、神学界にも大きな影響を与えたのです。文先生も「精子と卵子」の両方を述べます。そこに「両性の本質的平等」という神学思想を見ることができます。
2 「血統」と「遺伝法則」
また、文先生は血統と遺伝法則について次のように述べます。
「千代万代後孫が罪人になる善悪の実とは何でしょうか。これは血統的関係です。血統的に罪の根を植えておけば、遺伝の法則によって永遠に続くのです。そうであり得るのは愛の問題だけです。誤った愛が堕落の原因です」(『祝福家庭と理想天国Ⅰ』435頁)
このように、「血統」と生物学的「遺伝法則」は一体不可分です。
『平和神経』にも、「生命と愛が合わさって創造されるものが血統です」(126頁)とあり、また、文先生は第28回「真の神の日」で次のように語っています。
「生命を見ましたか?生命に触ってみましたか?生命体は見えるけど、生命は分かりません。触ってみることはできません。血統もそうです。血統は夫婦が愛するその密室、奥の部屋で結ばれるのです。そして、精子と卵子が出合って生命体として結合するとき、血統が連結されるのです」(「ファミリー」95年3月号22頁)
文先生の血統概念は、岡本言説のように「『心情的血統』か『生物学的血統』か」と二者択一的に問い、「心情」(愛)と「性関係」を分離するようなことはしません。文先生の説く血統は、「愛」と「性関係」(生物学的な精子と卵子)が一体となって形成される「血統」の概念です。神様の血統、あるいはサタンの血統というその血統とは、性関係を抜きにした「心情の関係」ではありません。ただし性関係と言っても、その血統連結は、禹明植集団における“天法”に違反する不倫による「血分け」ではありません。
ところで、岡本言説が「心情的血統」の概念の根拠とする「サタンの侵犯を受けない心情的血統の回復」(『救済論の問題点』172頁)という御言は、神様を父と呼べる「本然の血統」(実子=イエス様)を語っているのです。岡本言説は、御言の中から「心情的血統」という言葉のみを抽出することで、血統の概念を曲解し、模糊化させるのです。
四、「二つの救済観」という批判について
(一)岡本言説は、両性の生命を抜きにして、「性的関係」とは無関係に「神様の血統」を説こうとします。それが、彼らの強調する「心情的血統」の概念です。この概念によって、個人的次元における神様との心情一体化だけを説き、それによって神様の血統に連結できると強弁するのです。この主観的観念論の見解は誤りです。
まして堕落人間が「祝福」、すなわち「接ぎ木」(聖酒式による血統転換)を抜きにして、個人的次元でいくら努力(意識改革)しても、堕落性は脱げません。また、完成期に上がって神様と心情的一体化をすることもできません。
御言に、「神の心情は、どこからか飛んで来るのではありません。血統を正さないというと、元から、心情の栄養分が、心情の血統がつながりません。……蕩減復帰は、血統を求めて、それから心情圏を求めていかなければなりません」(『本郷』209~210頁、『誤りを正す』156頁)とあるように、「まず血統を正し、しかるのちに、神様の心情に連結されて心身統一が成されるのです」(前掲書255頁)
(二)ところで、『救済論の問題点』は、「法廷論的贖罪観」(「原罪」と「堕落性」の分離)という考えは、「反対牧師対策」がその背景にあって、“救い”を強調せざるを得ないという必要性から生まれてきた救済観であると述べています(56頁)。
しかし「法廷論的贖罪観」は、文先生が解明された真理による救済観です。何らかの条件(「必要な手続き」)で贖罪されるとは、「聖酒式」を言うのです。祝福とは、アダムとエバの堕落前の状態に復帰する式です。聖酒式は原罪を清算し、サタンの主管圏から解放、釈放される「万人救済の儀式」です。
聖酒式で、堕落の「経路」を反対に遡っていって原罪を清算し、その後「堕落の動機」、すなわち「堕落性本性」の消滅は、自己犠牲の愛を実践することでなされていきます。蕩減復帰の原理から見て、「原罪清算」(経路)と「堕落性本性」(動機)を脱ぐ道は、同時でなく、分離され、先後の関係にあります。
(三)さて、岡本言説は、『誤りを正す』の内容に対して、それを「万人救済論を否定する生物学的血統転換論」(160頁)であると批判します。
しかし、聖酒式によって、祝福家庭は「血統転換」しているのであり、神様の血統圏(皇族圏と王族圏)にすでに入っているのです。祝福一世も祝福二世も“皇族”であって、救われています。四大心情圏と三大王権と皇族圏を完成するために、祝福家庭は人類歴史上、だれも歩んだことがない完成期を、真の父母様のご家庭に侍りながら歩んでいるのです。神様の血統圏の中での「祝福二世と直系の結婚」は皇族から王族に入っていくことを意味します。
ところが、岡本言説の信奉者たちは、この「祝福二世と直系の結婚」のみを救いであると主張していると曲解し、私たちの主張に対し「万民救済論を否定する生物学的救済観」と揶揄します。しかし、結婚は「血分け」ではありません。また、皇族と王族は共に「神様の下の一つの家族」です。祝福は万人救済です。
「法廷論的贖罪観」とは祝福のことであり、岡本言説が揶揄している“生物学的血統転換論”とは、皇族と王族(真の子女)の結婚のことです。それゆえに、人類を救済する「二つの救済観」に対立や矛盾は一切なく、そこに深刻な問題もありません。
五、岡本言説による、軽視できない稚拙な批判(堕落論への疑念)
(一)妊娠に至らない淫行
「堕落論」の原罪観に対し、『救済論の問題点』は「妊娠に至らない淫行」(118頁)を取り上げ、子供ができて“血統が生じるまで”“不倫な行為”がアダムとエバの間に何回あったとしても原罪と認定されないのでしょうか、と批判します。
『講論』を注視してください。堕落論は「堕落の動機と経路、およびその結果」を論述しているのです。一部のある行為だけを指して論じているのではありません。
原罪という「堕落行為」(不倫関係を結ぶこと)は、アダムとエバの間の“肉的堕落”だけを指すのでなく、それより前にあった天使長ルーシェルとエバの“霊的堕落”をも組み込んでいます。また、「血統的な罪」とあるので、堕落行為の「結果」、出生する罪人も「原罪の概念」に含まれています。
それゆえ、妊娠に至らない「不倫なる行為」も原罪の定義の中(経路)にあるので、それは罪と認定されます。実際、御言にあるように、アダムとエバはエデンの園から追い出される前に子供を産みましたか?追い出されてから子供を産みましたか?彼らは取って食べた時、直ちにエデンの園から追放されたのです。
文先生は次のように語っています。
「堕落した後にアダム・エバをエデンの園から追い出したでしょう?ところで、アダム・エバは子供を生んだ後に追い出されましたか。愛の関係で堕落したとすれば、愛の関係を結んだことを知った後に、子供を生む時まで保留して追放するという法は無いのです。雷が落ちるのです。堕落したアダム・エバを見れば直ちに火が落ちるのであって、何日か待つことができますか。できません。絶対にできません。子供を生もうとすれば夫婦生活もするし、胎内で十か月は待ってから、『おぎゃー』と言って出て来るのです。ですから、結論ははっきりしているのです。堕落した直後、子供を生む前に追放されたということは間違いありません」(「祝福」76号=93年春季号120~121頁)。
(二)生物学的血統につながらない「霊的堕落」
天使長とエバの霊的堕落では子供はできません。一代限りです。エバだけの堕落であれば、容易に救済することができました。種であるアダムまでもが堕落したので、救いが延長してきたのです(『講論』111頁)。
天使長ルーシェルとエバとの不倫関係ですが、天使長が誘惑しても、エバが「取って食べてはならない」(創世記2章17節)という戒めを守り、天使長と相対基準を造成しなければ、二人の間に愛が現われません。したがってエバは一線を越えず、天使長は片思いに終わり、サタンの堕落性本性が人間の中に入ってこなかったのです。
すなわち、自己の位置を離れた天使長に「自己中心の動機」(堕落性本性)があったとしても、動機でとどまり、罪を犯すに至りませんでした。言い換えると、「動機(堕落性本性)が動機でとどまり罪にならなかった」、「天使長はサタンにならなかった」のです。
『講論』に「エバはルーシェルと愛によって一体となったとき、ルーシェルの要素をそのまま受け継いだのであった」(109頁)とあるように、天使長とエバの「堕落行為」の結果、サタンの性質(堕落性本性)が人間に入ってきたのです。
堕落の結果、エバの心情が汚れました(「本末転倒の論理」ではない)。言うまでもないことですが、天使長の堕落性本性は「心の中の動機」であって、原罪(淫行、外的な行為)ではありません(「原罪」と「堕落性本性」は同じではない)。「意思が結果の観念をもっていた」としても、そうだというのです。
『講論』が論述するごとく、すべての罪は原罪から来るのであって、原罪の前に多くの天法に違反する「罪」があったのではありません。
御言では、天使長ルーシェル(サタン)の自己中心的な「堕落の動機」を「悪と罪の源」と指摘しています(『祝福家庭と理想天国Ⅱ』268頁)。この「源」(動機)は、神様が悪なるものとして創造されたのではなく、本来善として創造されたものが悪なるものになったのです(一元論)。では、なぜ善が悪になったのかと言うと、それは「愛」によって引き起こされたのです。
『講論』は、「堕落性本性が生ずるようになった根本的動機は、天使長がアダムに対する嫉妬心を懐いたところにあった」(122頁)と述べます。この嫉妬心に関して、「創造本性から生ずる付随的な欲望は、人間の発展をもたらす要素とはなっても、決して堕落の要因とはなり得ない」(123頁)と述べています。
(三)「抱擁や接吻」について
岡本言説は、「一線を越えるという行為(淫行)の前に、既に抱擁や接吻等、多くの天法を違反する行為の連続があった」(『救済論の問題点』122頁)と述べ、そうであるなら“淫行”は「原初の罪」と言えなくなるのではないか、と疑念を主張します。
そして、「『原罪』の前に、沢山の『罪』が並んでいるという、とても奇妙な論述となり、『原初の罪』の定義とも矛盾する結果となってしまう」(同)と批判します。
『講論』は、天法に違反する血統的な罪(淫行)を「原罪」と定義します。「一線を越えること」を目的とした天使長の「抱擁や接吻」(122頁)は、血統的な「原罪」を犯す過程にあり、まだ違反していないにせよ、創造目的(神様のみ旨)に反しており、天法に違反しようとしているので問題とされます。
しかし「一線を越えず」、堕落行為に至らない場合には、天法に違反する原罪(原初の罪)の“未遂”に終わって、天使長の動機(堕落性本性)が人間の中に入ってこなかったというのです。その場合は、エバと天使長の救いは容易です。
(四)「淫行関係」と「血縁関係」の概念の混乱?
また、岡本言説は、次のように批判します。
『講論』は「淫行関係を結ぶことが、あたかも血縁関係を結ぶことと同じであるかのように表現しています。この表現が血統の概念に、大きな誤解をあたえてしまっている」(『救済論の問題点』132頁)。
彼らがこう述べて批判するのは、人間は「アダムとエバの後孫」であって、「ルーシェルの生物学的血統」のもとに生まれたわけではない。なぜなら、エバは「(肉体の)精子を持たないルーシェルの子を身ごもることは出来(ない)」(134頁)からであり、ゆえに人間はサタンとは血がつながっていない、と言いたいためです。
まず、なぜ『講論』にはそのように論述されているのかを考察すべきです。エバはサタンと愛の因縁を結び、“サタンの妻”となりました。そのサタンの妻となったエバが、今度はサタン的な愛でアダムと関係を結んで、アダムを堕落させたのです。この「淫行関係」の結果、アダムを“サタンの息子”として生み出したのです(悪なる血統転換)。
これは、御言に「堕落の責任は、サタンを中心として、エバから始まり、アダムに移りました。すなわち、偽りの生命の種を受けたエバの立場からすれば、神様に代わってサタンが父の位置でエバと(一体となって)、アダムを生んだ立場となり、堕落が成されました。こうしてエバは、天使長とアダムを各々父と息子のような立場に立てて堕落した」(「ファミリー」92年6月号58頁、『誤りを正す』115頁)とある通りです。
すなわち、サタン的な愛と性の諸関係によって、サタンとアダムとの間に「父子関係」を形成させ、サタンと「血縁関係」を結ばせたというのです。
文先生は、「愛には縦的愛と横的愛があるのです。父子関係は縦的愛であり、夫婦関係は横的関係です。縦的愛は血統的につながり、夫婦関係は血統的につながりません」(『訪韓修練会御言集』12頁)と述べています。この御言のごとく、サタンとアダムの「父子関係」は、縦的愛であって血統がつながるのです。
『講論』には、なぜ「霊的堕落と肉的堕落による血統的な罪」(121頁)と定義されているのでしょうか。また、なぜ「霊的堕落」と「肉的堕落」の2つを分離せず一緒にして定義しているのでしょうか。そのことを理性的に考察すべきです。『講論』の原罪の定義は、サタンの血統にいかに連結したのか、というその「経路」を示しているのです。
岡本言説の「心情的血統論」を盾にした「生物学的血統観」への批判の誤りは、愛と性関係を分離して見ているところにあるのです。文先生の説く血統の概念は、愛と性関係を分離していません。上述のごとく、サタンの“利己的愛”と“性の諸関係”による血縁関係の形成経路を見るべきです。
アダムとエバは、堕落人間のように「原罪ある人間」として生れた存在ではありませんでした。原罪のない「神様の息子と娘」として生まれましたが、堕落することで、アダムとエバの血統は、サタンの血統となったのです。
(五)性的行為を「淫行」と呼ぶ表現は不適切?
岡本言説は、「アダムとエバの堕落行為(肉的堕落)をなぜ『淫行』というのか、その表現は適切でない、今流でいえば『婚前交渉』ということで、現在の刑法では、倫理的には問題があるとしても、それほど重罪とされるわけではありません」(『救済論の問題点』121頁)と述べ、堕落論を批判します。
しかし、エバがサタンと愛の因縁を結んで(=霊的堕落)“サタンの妻”となり、そのサタンの妻となったエバが、堕落していないアダムと性関係を結び(=肉的堕落)、その結果、サタンと“父子関係”を結んでサタンと一体となった堕落アダムが、堕落エバと性関係を結ぶことは、「淫行」「淫乱」と表現する以外にありません。むしろ「婚前交渉」と表現する方が不適切です。
また、天使長ルーシェルとアダムとエバの間における「性的関係」(霊的堕落と肉的堕落)という行為は、そこから「サタンの血統」が出発したので“重罪”です。
文先生は「私が糾明した原罪と堕落の曲折は、人間の最初の家庭で起こった天使長との不倫の事件でした」(『天聖経』宇宙の根本、1863頁)と述べ、「天使長と不倫の関係を結んだというのです。これが宇宙を破綻させた根本原因になったのです」(『天聖経』罪と蕩減復帰、1231頁)と明言しています。
このように、天使長との不倫の事件が「宇宙を破綻させた」ので、これ以上の重罪はないというのです。
しかし岡本言説では、「『動機』や『思い』といった精神面より、やはり、違法『行為』という外的行為面のみが強調されてしまう傾向にある」(『救済論の問題点』126頁)、「より本質的問題は、性行為を通じて子孫に伝播した、『未熟、かつ自己中心であった性質(堕落性本性)』である」(同121頁)と述べ、アダムとエバの性質のみを問題視して、サタンの罪(淫乱)を隠蔽しようとします。
ところで、「性を通して子孫に伝播した」と言いますが、その伝播した「性」が問題なのです。結局のところ、岡本言説も原罪がどのように「伝えられていったか」ということになると、ホーダーンが指摘しているように、アウグスティヌスや堕落論の教義に頼らざるを得ないのです。
結論として、未成年の段階で誘惑されて犯したアダムとエバの罪(堕落行為)はどのように判定されるのでしょうか。それは「人間の罪は、サタンのように徹底的な刑罰と破壊の対象ではなく、〈あわれみ〉を誘うようなところがあり、したがって純粋な刑罰だけでなく同時に赦免や救済も聞かせられるべき対象なのである。それは神の刑罰の宣告が、へビと、アダムとエバに対し、区別して語られていることに暗示されている」(『キリスト教組織神学事典』教文館、268頁)ということです。
サタンの罪(淫乱)はこの「事典」にあるように、自発性にもとづく破壊的な罪なので重罪です。
(六)御言の「原罪観」は、プロテスタント神学に近い?
『救済論の問題点』は、『御旨と世界』から「愛の病気」の御言を取り上げ、文先生の思想は「『原理講論』の(不明瞭な)表記をもとに構築された現在の統一教会の『原罪観』よりも、むしろ従来のキリスト教(特にプロテスタント神学)により近い概念であることが分かってきます」(111頁)と強弁します。
ところが、この「愛の病気」の御言を注視すれば、文先生は「自己中心こそが『堕落の動機』となった」(同、110頁)と述べているのであって、「原罪」だと言っておられるのではありません。岡本氏らが、御言をそのように解釈するのは、プロテスタント神学の原罪観が正しいという“色眼鏡”で見ているからであって、これは、むしろカトリック神学により近い概念であるというべきです。
(七)統一教会の罪観は旧約的律法観?
岡本言説は、新約聖書の聖句を引用して、統一教会の罪観は「旧約的律法観」であると述べ、次のように批判します。
「『情欲をいだいて女を見る者は心の中ですでに姦淫をしたのである』(マタイによる福音書5章28節)と語られた新約聖書の『御言』をも“公然と否定する”結果となり、より内的動機や精神性を重んじたキリスト教の『罪観』より、はるかに次元の低い、まさに時代を逆行した旧約的律法観」である(『救済論の問題点』100頁)。
これは、プロテスタントがカトリック神学の「行い」による功徳思想を外的な律法主義と批判したのを、統一教会に置き換えて語っただけのことです。
プロテスタントの罪観は、「行い」を否定して内面を見つめようとします。それは一面において優れたところと言えますが、しかし他方において、社会性がないと批判されています。
また、イエス様が言われたというその聖句(姦淫の思い)は、堕落人間を対象として言われたのであって、裸でいても恥ずかしくないように創造されていた、純潔で無垢なアダムとエバにはなかった「思い」です。しかし、堕落人間にとっては、いかに努力したとしても、また、キリスト者になったとしても消滅させることのできない「思い」です。
パウロが「心と体の分裂」を呻吟したように、堕落人間には、後から後から「肉的な思い」(罪)がわき起こってくるのです。それはなぜでしょうか?サタンの血統を継承しているからです。われわれは「祝福結婚」によって血統転換し、さらに、自己犠牲の愛を実践しない限り「心情革命」(「心の革命」)は、到底なし得ないのです。