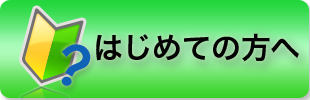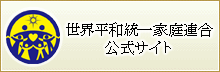似非「祝福二世相談室」の誤りを正す
一、「人間の堕落、その罪の起源と諸問題」
1995年1月、反対牧師の『講論』批判の代弁者、飯干晃一氏(故人)は、自著『イヴは淫乱だったか?』(祥伝社)で次のように述べました。
「キリスト教は、人類始祖のこの神への不服従を人間の原罪と呼んだ。しかし、じつのところはこの不服従だけが罪ではない」(79頁)
確かに、性質(精神性)が原罪なら、いろいろな性質が挙げられます。それでプロテスタント神学はいろいろな「性質」の中から、「罪の本質」とは何かを問います。神学者によって「罪の本質」は相違しますが、利己心、誇り、不信仰、不従順、不服従などとします。いずれにせよ、罪は内的な性質(精神性)と見るのがプロテスタントの原罪観です。
(一)プロテスタントの罪概念
ヘンリー・シーセン(AD1883~1947)は、「罪は行為となって外に表われる以前に、すべての人の内に、性質として存在している」「外に表われた行為は、それが悪の性質に根ざしている」「刑法は犯罪の行為そのものよりも、その動機にもっと関心を寄せている」(『組織神学』403~404頁)と述べます。
そして、罪の概念を「罪が実際の行為だけに限られるべきではなく、その中から罪が起こってくる状態をも含む」(同)と規定します。聖書で言う「暗くなった知力」「邪悪なむなしい思い」「恥ずべき情欲」「悪い言葉」「汚れた知性と良心」「邪道に陥った意志」など、これらは“腐敗した性質の源”から出てくる徴候だと見ます(同405頁)。
そこで、シーセンは「キリスト者は、神の律法から離れるのは自分のうちに堕落した性質があると考えて、実際の罪の行為よりも、もっと深くそれを悔い改める」(同404頁)と言うのです。
しかし、『講論』が指摘しているように、篤信者が「悔い改め」ても、後から後から「罪の思い」(「肉的に入ってくる罪悪」187頁)がわいてくるのはなぜか、という問題があるのです(十字架の救いの限界性)。また、人間がそのような「罪ある存在」になぜなったのかという、より根源的な問題があります。
(二)罪の本質について
シーセンは、罪の本質について次のように述べます。
「罪の本質は利己主義である。何が罪の本質的原理であるかを、決定するのはむずかしい。『アウグスティヌスとアクィナスは、罪の本質を誇りであるとし、ルターとカルヴァンは、その本質を不信仰であると考えた』。しかし、これらはいずれも、罪をその究極の性質にまでつきとめていない。聖書が、敬けんであることの本質は神への愛である、と教えている以上、罪の本質は自己への愛である」(『組織神学』406頁)
このようにシーセンは、「罪の本質は利己主義である」とします。そこから他のすべての罪が起こってくるというのです。このような見解の追従が、岡本言説であるのは一目瞭然です。
(三)「文先生の御言」研究
1 “自己中心”は堕落の動機である
同じく文鮮明先生(真のお父様)も「悪とは、この世界への利己心の顕現であります。神の利他的な与える原理は、神ならぬ利己的な奪う原理へとゆがめられてしまったのです」「悪の根源はサタンであります」「彼の動機は利己心でありました。彼の利己心から悪と罪の源が出てきたのです」(『御旨と世界』266頁)と語られます。
シーセンとの一致点は「罪の本質」「悪と罪の源」が利己心(堕落性本性)であるという点です。
異なる点は、
①シーセンは、「悪の根源」のサタンと、人間の関係を明らかにしていない。
②御言は、サタンの利己心は「動機」であるとし、利己心(堕落性本性)を「原罪」であるとは述べていない。
③シーセンは「自由意志」によって堕落した(409頁)と述べるが、御言は「非原理的な愛」によって堕落したとする。つまり自己中心は動機であり、「自由意志」で堕落したのではないとする(『講論』127頁)点です。
2 対象との関係(「与える原理」と「奪う原理」)
文先生は、「我々人間のすべての特質は、神から来ているのであります。我々は、人間には利己的な傾向があるということを知っています。これはある一時期、神ご自身が自己中心的であられたので自然なことなのです。この事実はあなたを驚かすかもしれませんが、しかし、神は人間と宇宙とを創造される前は、たった一人で、御自身以外の何ものをも意識することなく存在しておられたということを理解しなければなりません。しかしながら、神が創造に着手されたその瞬間……神は、今や、ご自身のためではなく、その対象物のために生きるようになったのです」(『御旨と世界』262頁)と述べます。
御言にあるように、「たった一人」のときと「対象物」があるときの相違を認識しないと、「神ご自身が自己中心であられた」を誤解するのです(参照、『誤りを正す』180頁)。
対象との関係は「与える原理」であって「利己的な奪う原理」ではありません。対人関係において「利己的な奪う原理」をつくったのはサタンです。堕落人間は「与える原理」(心に神の律法)と「利己的な奪う原理」(肢体に罪の律法)が熾烈に闘っているのです(心と体の分裂、ローマ人への手紙7章23節)。
(四)プロテスタントの「性質原罪論」の問題点
プロテスタント神学の「内的な性質」に原罪があるとの見解には、多くの神学的問題があります。人間の堕落性が、先祖から受け継いだにしろ、習慣や経験のうちに固着したにしろ、すべての人間に原罪があることは事実です。
しかし、①いかにしてその罪が発生したのかという問題が未解決のままです。また、②神がそのような「罪への傾向性」を持つ人間を最初から造ったのかとの疑問があります。もしそうならば、人間は永遠に救われないし、社会から絶対に悪と罪はなくならないことになります。しかし、罪を裁く神は、悪と罪の根源ではありません。それで、③「罪の気質」がどのようにして「アダムの性質の中に入り込んだのか」という疑問が生じます。また、④罪が「内的な性質」にあるという見解には、シーセンも指摘しているように「神に責任を負わせ、人間を罪のとがから解放することになってしまう」(『組織神学』408頁)という問題点を内包します。それゆえ「性質に原罪がある」といえないのではないかと言うのです。
なぜ、文先生が性質(自己中心)を「堕落の動機」とし、「原罪」と言われないのかを明確に知るべきです。
飯干氏の『イヴは淫乱だったか?』には、上述の問題意識はありません。いや、ないどころか、むしろ救われない現実を認めて、「人類は絶えず罪を犯すものである」(140頁)と言う始末です。このような「性質原罪論」は、プロテスタント神学がそう見ているからであり、岡本言説にも同様の問題点があります。岡本氏は、一応「神義論の迷路」(『救済論の問題点』86頁)と言うには言いますが、やはり「自己中心性をもった個の実体の確立という『個体的段階での堕落(第一祝福型の堕落)』として起きている」(同87頁)と強弁します。ゆえに、なぜ心に罪が生じたのか、神がそのような心を造ったのか、という問題が残ります。
堕落性本性(自己中心)がどのように発生し、どのようにしてアダムの性質の中に入り込んだのかに関して、結局のところシーセンは「一体、どのようにして、この初めの汚れた思いがきよい存在者の心の中に起こったかはわからない」(『組織神学』409頁)と正直に述べます。ところが、「内的な『動機・性質』としての原罪」(第五弾、反論―11)であると強弁し続ける岡本氏らは、「わからない」と正直に言うことをしません。
以上のように、プロテスタント神学の性質原罪論には多くの問題があり、そう断言できないと言うのです。それで、W・E・ホーダーンは、「人間の病」の根源こそ「精神的なもの」であるが、「しかしそれがどのようにして始まり、どのようにして伝えられていったかということになると、アウグスティヌスの、アダムとその罪の遺伝についての教義を、学ぶ必要がある」(『現代キリスト教神学入門』47頁)と言うのです。
(五)「堕落論」による統一
御言によると、原罪(血統的な罪)とは淫行(結果)であって、ホーダーンのいう「精神的なもの」とは利己的な愛(原因)です。堕落とは、この「愛によりもたらされた結果」なのです。
原罪論の統一とは「容易なわざではない」が、一方の罪の遺伝説を退け、他方の心理的分析だけを受け入れることではありません。堕落の原因となった「堕落の動機」(心理的分析、堕落性)と、その結果である「原罪」(生物的遺伝的側面、血統的な罪)の双方を「動機と経路」として解明したものが、「堕落論」に他なりません。
心理的分析に偏った岡本言説ではキリスト教統一は不可能ですが、“堕落性本性”と“原罪”の双方を解き明かした「堕落論」によってのみ、キリスト教統一が可能なのです。
(六)岡本氏らは思想転向者
岡本言説の原罪観は、「堕落論」の概念ではありません。シーセンと同じ「罪の本質」の概念です。この「性質原罪論」のフィルターを通して、文先生の「愛の病気」の御言(「自己中心こそが『堕落の動機』となった」)を見ているのです。それで、御言は、動機(自己中心)を原罪だと述べていると強弁するのです。彼らは「堕落論」の原罪論を放棄した、いわば「思想転向者」であり、思想戦における敗北者です。
二、「分子生物学」の観点からの「堕落論」批判
(一)「既存の遺伝説」と「血統の遺伝」の混同
飯干氏は、プロテスタント神学の立場から、内的な性質(精神性=罪への傾向性)に原罪があると述べ、「堕落論」の原罪論(淫行、血統的罪)を批判し、また「サタンの血統」に関し、浅見定雄氏の「分子生物学」の観点から「珍説」だと揶揄し、「科学的に説明せよ」と批判します。
しかし、「堕落論」でいう「罪の遺伝」とは、反対派が否定する既存の遺伝説ではありません。「罪を犯せば遺伝子が変わり」「罪が生物学的な遺伝情報として子孫に伝えられる」と言っているのではないのです。それは、「堕落によって血統が変わり、サタンの血統が遺伝法則によって伝えられている」「原罪とは血統的遺伝的なもの、そうであるのは愛の問題以外にない」と言うのです。
反対派は「既存の遺伝説」と「血統の遺伝」とを混同しているのです。岡本氏らも同じです。
(二)反対派が「珍論(オカルティズム)」と言う理由
浅見定雄氏は、霊的存在である天使長とエバの「性関係という行為の結果が血統(サタンの血統)として残るとは、古代人の考えならまだしも、分子生物学の時代の話としては呆れた新説である」(『統一協会=原理運動』132~133頁)と批判します。
飯干氏も、「統一教会の説く人類の悪魔血統説など、できの悪いオカルティズム」(『イヴは淫乱だったか?』141頁)と批判し、「天使は霊であって肉体がないのだから、性交は不可能である」(同115頁)と言います。こう述べるのは、霊的存在である天使長とエバが性交して子供が生まれるのか、という反対派の見解(疑念)に追従してのことです。
これで、なぜ浅見氏らが堕落論を「珍論」と言うのか、理由がよく理解できます。
(三)「サタンの血統」説を科学的に説明せよ
「堕落論」は「堕落した人間は神の血統ではなくサタンの血統をもって生まれた」「悪魔の子孫」(『講論』102頁)と述べます。聖書においても、イエス様が「あなたがたは自分の父、すなわち、悪魔から出てきた者であって、その父の欲望どおりを行おうと思っている。……彼は偽り者であり、偽りの父であるからだ」(ヨハネによる福音書8章44節)と語っています。
飯干氏は、この「サタンの血統」説に対して「生理学的に証明せよ」と言って、次のように噛み付きます。
「エバが悪魔と性交したので、エバが悪魔の血に転換した、という珍説をひとつ科学的に説明してくれんかね。それを生理学的にも医学的にもどうやって証明するつもりか?あんた方が科学を軽々しく口にすれば、科学が泣くというものだ。しかも、その悪魔の血が子孫に遺伝すると言うに至ってはひっくりかえる」(『イヴは淫乱だったか?』94頁)、「できの悪いオカルティズムである」(同141頁)
(四)道徳と原罪観
そして、飯干氏は「人間には原罪がある。そのために人類は絶えず罪を犯すものである。それを人間に強く自覚させるキリスト教の原罪論は、さすがに道徳論として非常に価値が高い」(同141頁)と述べ、「性質原罪論」を持ち上げます。
岡本言説も、この主張の「ものまね」をして、統一教会の罪観は旧約的律法観で、「内的な精神性を重んじたキリスト教」の方がはるかに「道徳的」に高いと述べます。
(五)天使と人間の娘の結婚話
ところが、飯干氏は、統一教会が言う創世記の「天使と人間の娘の結婚話」を取り上げ、これをいかに解明するかで、13世紀の神学の最高峰トマス・アクィナス(AD1225~1274)はずいぶん悩んだと述べて、次のように論じます。
「彼は霊的存在である悪魔が人間の女性と性交し、いかにして妊娠せしめ、悪魔の子を生ますかについて、アウグスティヌスの論法を援用しながら、彼の著作『神学大全』で次のように論証した……『悪魔が人間の女を犯し、悪魔の子を生ますことは可能である。しかし、なぜ精液を持たぬ霊的存在である悪魔が人間の女を孕(はら)ますことができるのか。それは、悪魔は女色魔となり男からうけとった精液を、こんどは男色魔となって女の肉体の中に注ぐことができるからである』。この論証と統一教会の論旨とを比較してみると、同じく荒唐無稽ながらもトマス・アクイナスのほうが、はるかに確固とした生理学的見解に立っていることが分かる。科学、科学と騒ぐ統一教会はこのトマス・アクイナスのツメのアカでも煎じて飲むがいい」(同116頁)
このように、「サタンの血統」説をめぐって、反対派は生理学的にどうの、科学がどうのといろいろ論じますが、それらの言い分のすべてを聞いてみると、霊の理解で混濁したトマス説を引用した飯干氏だけが、反対派の神学思想から突出しており、「サタンの血統」概念の理解において、統一教会側の見解へ一歩近づいています。
しかし、分子生物学の時代に、御言の文脈から「心情的血統」という言葉のみを抽出し、「サタンの血統とは『心情の血統』である」として、生理学(生物学)と無関係なものと強弁する頑迷な岡本言説は、無知蒙昧に陥っています。彼らこそ、トマスのツメのアカを煎じて飲まなければなりません。
ところで、万人救済とは「血分け」を否定する「祝福」を言うのです。
三、ルターが抱いた疑問点
マルティン・ルター(AD1483~1546)は、「どうして神は、アダムが堕落するのを許したもうたのか。また、神は彼を堕落せぬように保つか、あるいは私たちをほかの裔(すえ)からか、または清められた第一の裔から造ることができたもうたであろうに、どうして私たちすべてを同一の罪にけがされたものとして造りたもうたのであるか」(『ルター』松田智雄、223頁)と述べます。
そして、「神秘を探ることは、私たちのなすべきことではない。むしろ、この神秘を畏敬すべきなのである」(同)と言います。しかし再臨主の理性は、この神秘を解かなければならならないのです。
また、フランシスコ・ザビエル(AD1506~1552)に対し、鹿児島の住人が次のような疑問を提起したという話があります。
「確かに悪魔が存在し、それが悪の原理であり人類の敵であることはわかるが、それなら創造主を認めることができなくなる。何故なら、万物を造ったといふ善なる創造主が悪を造り出したといふのは矛盾だからである……もし創造主が人間を造ったと言ふなら、自分が造った人間が悪魔に誘惑された時、何故人間を保護せず誘惑されるのを黙認したか」(小堀桂一郎著『国民精神の復権』65頁)。
これらの論難は、文先生が鑑定してつくった「堕落論」を知っている人なら、難なく答えることができるのです。
四、無知蒙昧な「統一原理」批判
岡本達典氏らは、似非「祝福二世相談室」(ホームページ)の「統一教会の対応」の項目で、「『原理講論』を勝手に修正しているのではなく、あくまでも文(鮮明)先生の『御言』との相違点を指摘しようとしている」(第三弾、反論―06)と白々しいウソを述べます。
(一)『講論』に対する矛盾した価値認識
岡本氏らはその反論で、『講論』の「絶大なる価値を決して否定していない」「宗教の『教典』の中で最も優れた『教典』である」と認めているとします。しかし「過渡的段階性」(部分性)や「人間的要素の混入」が含まれるとし、「完成段階としての文先生の『御言』と『原理講論』を比較した場合、そこに『聖書』と同様の神学的(教典論的)課題が存在している」(はじめに、反論―02)と主張します。
岡本氏らは、褒めては貶(おとし)めるやり方をします。『救済論の問題点』では、『講論』は聖書の聖句を多く引用するので「まるでキリスト教の一つの派に過ぎないかのように見える」(26頁)とこき下ろしていながら、今度は「絶大なる価値を決して否定していない」と述べます。こんな矛盾した発言がよくできたものです。
(二)御言と『講論』は違うのか?
岡本氏らは、「『原理講論』も『御言』も、共に『文先生の御言』であるというのは、『聖書』の逐語霊感説を信じているファンダメンタルなクリスチャンと同様に……現実を無視した非科学的で乱暴な見解であり、『原理講論』は決して、文先生が劉孝元先生の手を握って書いたものではありません」(第三弾、反論―05)と述べ、御言と『講論』の違いを主張します。
聖書は、イエス様が亡くなった後で編纂されました。しかし『講論』は文先生が「一字一句」を鑑定した本です。聖書の編纂と同じではありません。聖書がイエス様によってつくられたなら「逐語霊感説」は正しいとされたでしょう。上述の反論は、聖書と『講論』の編纂の違いを認識しない無知蒙昧な批判です。
ちなみに、ブルトマン(AD1884~1976)は『イエス』(未来社)で、「私達はイエスの生涯や人となりについては少ししか知らない」(16頁)と述べ、人々に衝撃を与えました。共観福音書(AD60~90年代)は、客観的に歴史的事実を記した書ではなく、「はじめに教団(宣教)ありき」の立場で編纂された原始教団の信仰の所産であり、ゆえに福音書から“史的イエス”を復元することはできないと言うのです。
五、カットした、悪質な御言引用
それでは、どちらが真理を語っているのか、文先生の御言で検証しましょう。
「原理の御言を全部、本を読みながら講義するのです。『原理講論』は劉(孝元)協会長が書いたのではありません。一ページ、一ページ(先生の)鑑定を受けたのです。私が成したことに手をつけることはできません。ありとあらゆるものが、皆そろっているのです。間違っていたとしても、それを知らないのではありません。間違っているところ何ヶ所かを、そのままにしておかなければならないのです。すべてを教えてあげるわけにはいかないのです」(『誤りを正す』270頁)
『講論』に対し、文先生は「ありとあらゆるものが、皆そろっている」とし、「間違っているところ」は「何ヶ所か」と言われるのであって、教義の本質面(原罪や血統の概念)で「間違いがある」と言われているのではありません。もし原罪概念に「間違い」があれば、そのとき、放置されないでしょう。「堕落論」も「一ページ、一ページ(先生の)鑑定を受けた」と読むべきです。
岡本氏らは、悪質にもこの御言の罫線部分をカットして引用し、ホームページ(「はじめに」)や『100ヶ条の提題』(177頁)で取り上げますが、その関心は「間違っている」という言葉のみの抽出にあります。「何ヶ所か」も、やがて「間違っている部分」が「数多く含まれている」(同188頁)に誇張され、その挙げ句、「真理の一部分」である「古い時代の原理講論」(同432頁)に「しがみつくな」と言う始末です。しかし文先生は『講論』の破棄ではなく、「『原理本体論』が出てきた後に、『原理講論』は、その中にすべて入っています」(「ファミリー」09年4月号12頁)と語られています。彼らの自称「純粋に文先生の『御言』にのみ基づく」研究(第七弾、反論―13)とは、上述のごとくです。
(一)「『御言』全体の中にある普遍的真理(原理)」とは何か
岡本氏らは次のように述べます。
「『原理講論』が、先生がつくった御言の剣、天的な宣言であるとの表現はありますが、『神様の心の中にある主流の憲法』については、ただ『原理』とのみ語られており、それが劉孝元先生の書かれた書物としての『原理講論』そのものを指しているというよりも、文先生の語られた『御言』全体の中にある普遍的真理としての『原理』を指していると捉えることのほうがより的確な解釈」(はじめに、反論―02)
ここでも『講論』と「御言の中にある原理」との相違を必死で説こうとします。では、普遍的真理としての『原理』とは何でしょうか。「偉大な統一教会の『原理』」(『天聖経』宇宙の根本、1725頁)と御言にあるように、それは文先生が鑑定した『講論』であり、鑑定を受けていない岡本言説の言う「成約原理」ではありません。もちろん、『講論』には「保留部分」がありますが、この「保留部分」と『講論』の内容には対立や矛盾はなく、共に「原理」です。
(二)姑息な知恵
岡本氏らは、「“文先生は八つの分野においてチャンピオンである”との内容も、『原理講論』からの引用ではなく、『平和神経』13番、16番のメッセージからの引用であり、『原理講論』の文字表記が『御言』と完全に一致している(一体である)のかどうかを論じている文脈においては、全く論点がズレている」(はじめに、反論―03)と反論します。
しかし、「8つの分野においてチャンピオン」といわれる根拠は『講論』です。『講論』の「一ページ、一ページ」は文先生の「鑑定」を受けたのです。それでレバレンド・ムーンの『原理の本』(『祝福家庭と理想天国Ⅰ』57頁)と言われるのです。
『講論』の表面的な「文字表記」が御言の「文字表記」と完全に一致しているかどうかを「一体」と言っているのではないのです。「論点がズレている」と書くのは姑息な知恵です。反論や批判は詭弁によらず、もっと意味あることを言ってもらいたいものです。
(三)比喩や暗号はメシヤが解く
岡本言説では、『平和神経』に「天国へと導いてくれる鍵を持って来られる方」(329頁)とある「鍵」は、「再臨主として来られた文先生の使命について述べている」(第四弾、反論―07)と反論します。そして「天国へ導いてくれる鍵」と「比喩や暗号で語られた文先生の『御言』を解く鍵という概念とは全く異なる」とし、「神の立場で語られた文先生の『御言』を、『復帰された天使長』の立場で解明する人物が登場しなければならない」(同)と主張します。
岡本氏らは「比喩と象徴」(暗号)を解く「鍵」の必要性を語り、あれこれ詭弁を弄しますが、それがどういう意味か、誰が解くのか、文先生の御言で検証してみましょう。
「聖書を中心とする各教団の主要な経書は、人間始祖の堕落によって無知に陥った人間たちを、再び神様の前に帰す道が暗示されている秘密の啓示書です。したがって、重大な内容が比喩と象徴で描写されているのです。比喩と象徴は、天から来るメシヤによってのみはっきりと明らかにされます。したがって……レバレンド・ムーンの教えを通して、新旧約の聖書全体に貫き流れる神様の救援摂理に関する天の秘密が、明確に現されているのです」(『平和神経』282~283頁)
この御言にあるように「比喩と象徴」(暗号)は、天から来られる「メシヤ」によってのみ「明らかにされる」のであり、「復帰された天使長」の立場の人物によって暗号が解読されるのではありません。
堕落して「御言」を失ったのはアダムです。ゆえに、御言はアダム(メシヤ)が取り戻すのです。岡本言説の解明する「鍵」とは、パンドラの箱を開ける鍵です。
六、2000年のキリスト教史における神学問題
岡本氏らは、「『原理講論』の表記をもって、2000年のキリスト教史における神学問題が、あたかも全て論じ尽くされているかのような言い方は、明らかに神学的無知を曝(さら)け出したもの」(はじめに、反論―03)と反論します。
「宗教の『教典』の中で最も優れた『教典』である」と言っていたにもかかわらず、『講論』に対して何と無知なことを言うのでしょうか。では、具体的に論駁しましょう。
(一)イエスの先在性と復活、および原罪について
既存の神学は、イエス様がアブラハムより先にいたという「イエスの先在性」を説き、それはヨハネによる福音書第1章の「言葉(ロゴス)」賛歌が示すように、世の始まりまでさかのぼり、「神」と等しき存在者であるとします。現代人の理性では信じがたい使信(メッセージ)です。また「死人の復活」では、ブルトマンが「史的な客観的な出来事」ととらえないで「実存論的」に「主観的に解釈」(自己理解)し、バルトが「客観的な出来事」として「信じる」と論争した「復活者イエス」の問題、そして「原罪」(善悪の果を取って食べる)についてもそうですが、分子生物学の時代の現代人にとって理性的に不可解なこれらの「啓示」を、『講論』は「キリスト論」「復活論」「堕落論」で見事に解明しています。
これらは、ボンヘッファー(AD1906~1945)の言う「聖書の使信に対する非宗教的な解釈」です。
ちなみに「復活」と「原罪」について、遠藤周作とめぐり会い、カトリック信者になった安岡章太郎氏(芥川賞作家)と井上洋治氏(司祭)の著『我等なぜキリスト教徒となりし乎』(光文社)で、安岡氏は次のように述べます。
「はっきり言って、いったん死んだ肉体の復活というようなことは、あり得るべきものとは、僕は思わない」(89頁)、「もう一つの難問は『原罪』です。人間は生まれながらに罪を背負っているといわれても、それはそうかもしれないが、そんなことを言って、それでどうなるのかという正直な感想があります」(92頁)
『講論』は、その他,「三位一体論」や「空中再臨」など、多くの神学的難問に対し、それを「知性の犠牲」を強要して「信ずるべき事柄」としてではなく、「宗教と科学が一つの統一された課題」として理性的に解いています。
『講論』には、2000年の歴史を持つキリスト教を統一する内容(8つの分野のチャンピオン)があるのです。
(二)統一原理による「カトリックとプロテスタントの統一」
次に、キリスト教の統一に関して、文先生の御言で判断しましょう。
「キリスト教も、世界的な頂上で旧教(カトリック)と新教(プロテスタント)を一つにするには、統一原理しかないのです。そのように、歴史においてこれまで不可解だった聖書の内容を明らかに解明しているので……その道をたどっていかざるを得ないのです。統一せざるを得ないのです」(『男性訪韓修練会御言集』222頁)
キリスト教を統一するには、統一する神学内容がなければなりません。それが統一原理です。しかし岡本言説は、「統一原理と『原理講論』を混同してはならない」(「公開討論会」06年2月21日)と必ず難癖をつけます。詭弁術は相変わらずです。
(三)神学者や科学者が探求してきた「新しい自然神学」
岡本言説の無知蒙昧な主張は次のとおりです。
「森氏は……その他、カント的神認識を批判した、ティリッヒの存在論的な神概念を取り上げ、統一原理に対する洗礼ヨハネ的神学であったと述べていますが、そのことと、『救済論の問題点』が指摘している『原理講論』の問題点とは、全く論点がズレており、『原理講論』には『カントの神認識の問題点』や『ティリッヒの存在論的神概念』と文先生の思想との関連について説明した箇所はありません」(はじめに、反論―03)
1 『講論』(御言)と「カント哲学」の関連性
イマヌエル・カント(AD1724~1804)は、「存在者の存在目的」を否定し、因果の法則による神(第一原因)の存在証明を「独断論の妄想」(『純粋理性批判(中)』岩波文庫、164頁)とし、経験の「対象の領域外」(同158頁)と批判します(第一原因の原因は、と無限に続く)。そして「神の実在を、最高善を可能ならしめる必然的条件として要請されねばならない」(『実践理性批判』岩波文庫、250頁)とします。このカント哲学は、自然神学(神の存在論的証明)を否定し、神認識は信仰からという「福音主義」の哲学化です。
カント哲学と同様、福音主義神学の「客観的存在に根拠をもたない信仰による神認識」は、神を心情の枠内(家庭的四位基台に根拠をもたない個人が信じる主観的観念)に幽閉し、自然界をもっぱら無神論や唯物論の独壇場にさせます。これは知性の怠慢です。
神様と、疎外されている人間とを解放するために、なぜ「勝共理論」(弁証法的唯物論の批判と克服)が重要か、それを理解すべきです。「勝共理論」の根源である『講論』の「創造原理」は、ニュートン時代から神学者や科学者らが探求している新しい自然神学(存在の原理)です。
また、『講論』の「キリスト論」(創造目的を完成した人間とイエス)から見ると、「創造原理」はバルトらの「福音主義神学」(キリスト中心主義)を包摂します。
文先生の御言は、創造目的(存在目的)に対し「主体と対象があれば、必ず目的があって方向性があります」(『天聖経』宇宙の根本、1773頁)、「今日では、物理学が発達し、すべての原子にも意識があるという……この理論は、統一教会の二性性相原理の御言と同じです」(同1774頁)、「原因がない結果は、あり得ません。因果法則を否定する科学論理というものは、あり得ない」(同1784頁)と述べています。
2 『講論』(御言)と「ティリッヒの存在論的神概念」の関連性
偉大な哲学者や神学者は二つに分かれ、一方は自然神学を攻撃し、他方は弁護してきました。ティリッヒは、バルトの福音主義神学に対し「神を超自然の領域に幽閉している神学」「認識の基礎に信仰をおく不合理な信仰主義」と批判します。彼は、究極者(神)を「存在自体」であり、「存在の力」(「万物の中にある存在せしめる力」「万物を目的に導く力」)とします。この「存在の力」とは『講論』の「万有原力」のことです。
そして、「存在の力として神はすべての存在と存在の総体(世界)とを超越する」(『組織神学』第1巻300頁)と述べ、「存在自体の構造は、それが他のすべての事物の運命であるように、神の運命となる」(同299頁)とします。
この「存在自体の構造」とは「創造原理」の四位基台です。ハイデガー(AD1889~1976)が「〈存在〉とはなんであるか?」(『存在と時間(上)』岩波文庫、23頁)と問う、その存在です。
ティリッヒ神学の「存在の力」に関して、御言は「万有原力は、神様の本質的力をいうのです」(『天聖経』宇宙の根本、1794頁)、「すべての存在に内的作用の力を起こすことができる本然の宇宙力がある」(同1771頁)と述べています。
以上のように『講論』には、すべての哲学や神学を統一する内容があり、『救済論の問題点』が言うような一宗一派の教えではありません。論点はズレていません。「天的宣言」と言われる『講論』は、現代神学思想の最高峰です。後に「原理本体論」が出れば驚嘆します。