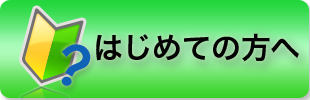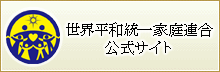梅本憲二氏(777双)から、特別寄稿文「真のお母様の時代に生きる」が寄せられました。梅本氏は、統一運動における「超教派部長」を担当。キリスト教信仰に造詣が深く、著書には『日本と世界のやさしいキリスト教史』『やさしい聖書学』『やさしいキリスト教神学』(いずれも光言社)があります。
『世界家庭』2024年2月号に要約版が掲載されましたので、掲載します。「ここをクリック」
* * * * * * * * * * * *
特別寄稿文 <信仰手記>
真のお母様の時代に生きる
――ユダヤ・キリスト教の伝統との対比の中で考える――
文責:梅本憲二(777双)
はじめに
昨今の統一運動における内外の状況を見るとき、今まさにわれわれは、一つの大きな摂理的峠を越え行く時に来ていると言える。このような摂理的重要局面を、勝利的に越え得るか否かは、ひとえにわれわれが、真のお母様と一つになって歩み得るか、否かにかかっているといえるであろう。
ところで、今日の統一家の食口たちの中には、――すでに「真のお母様の時代」に突入しているのであるが――、まだ新しい摂理的時代に十分乗り切れていないと思われる人たちのいることも事実である。
そこでこのような状況も踏まえた上で、今一度「真のお母様の時代」に生きる意味を考えてみたいと思う。
なお、ここに述べる内容は、あくまで私個人の信仰告白的内容(信仰手記)であり、「世界平和統一家庭連合」(以下「家庭連合」と略す)の公式見解ではないことをあらかじめ断っておきたい。
1 「真のお母様の時代」の到来
真のお父様の聖和とともに「真のお母様の時代」が始まった。もちろん全天宙的次元からいえば天の摂理は、天の父母様、真の父母様により牽引されているわけであるが、〝地上摂理〟という観点から見れば、真のお父様の聖和後、その直接的な牽引者、中心者は、真のお母様に移ったといえる。そういう意味で今われわれは、まさしく新しい摂理時代すなわち「真のお母様の時代」に生きているわけである。
ところで、冒頭でも触れたように、もうすでにここまで話を進めた段階で、一部の人たちから「真のお父様の後継が真のお母様であるということを、いま一度はっきり説明してくれないか」との声がかかりそうである。
実際、「統一運動」においては、前々から小さな次元での霊的集団等の問題は散見されてきたが、真のお父様の聖和以後、看過出来ない非原理的集団の問題が発生してきた。それらを支持する人たちは、真のお父様の後継を真のお母様と認めず、他に求めようとするところに特徴がある(注1)。
ところで、真のお父様の後継の問題については、すでに本部の教理研究院や家庭連合の「真の父母様宣布文サイト」を通して十分な解答――お父様の後継は真のお母様であること――が示されているが、確認の意味を込め、以下にその内容を私なりに簡潔にまとめておいたので、目を通していただければと思う。
すなわち、後継の問題についての真のお父様の代表的なみ言は、以下の通りである。
・「先生が霊界に行くようになればお母様が責任を持つのです。その次には息子・娘です。息子がしなければなりません。息子がいなければ、娘がしなければなりません。後継する者が誰だということは既に伝統的に全てなされています」(「マルスム選集」=以下、「選集」と略す。318-260、2000・3・10)
・「これからは先生がいなくても、お母様一人でみ旨に何の支障もないというのです。……先生が一人でいても真の父母様の代身であり、お母様が一人でいても真の父母様の代身です」(「選集」、201-126、1990・3・27)(『真の父母の絶対価値と氏族的メシヤの道』光言社=以下『絶対価値』と略す。115~116頁)
・「お母様を中心として皆さんが一体になっていかなければならない時が来ました。もう先生がいなくても、お母様が代わりにできる特権を許諾したというのです。お父様がいないときは、お母様のことを思わなければなりません。……先生の代わりにお母様に侍る心をもち、祈祷もそのようにするのです。今までは先生を愛してきましたが、これからはお母様を愛さなければなりません。これからはお母様の時代に入っていくことを理解して……ここにおいて、先生が第一教主であれば、お母様は第二教主であると世界的に宣布し、天地に宣布します」(「選集」265-310、1994・11・27)(『絶対価値』116~117頁)。
・「お母様は、お父様よりももっとたくさん行います。年齢が若いので、私が死んでも教主は問題ありません。もはや、教主は二人が一つになっているということです」(「選集」541-146、2006年9月28日)
・「お母様は、第二教主の資格がありますか、ありませんか。大講堂に立って凛々しく、男性のような度胸をもってお母様以上に講演できる人は手を挙げてみてください。……お母様がここまで立派にできるとは夢にも思わなかったでしょう。大いに尊敬しなければなりません。先生はもう七十を超えてくずかごに近づきましたが、お母様は今、そのくずかごを収拾してすべて掃除できる主人になったので、先生よりも、お母様をもっと重要視できる統一教会員になれば福を受けるというのです」(「選集」220-236、1991・10・19)(『絶対価値』118頁)。
・「文総裁は衰えるようになりましたが、……第二教主には、お母様が堂々としているでしょう。分かりますか。夫が成せなかったことを成し遂げなければなりません」(「選集」540-73、2006年9月23日)
・「父の伝統に従って、母の伝統に従って、三番目に息子である。それを知っているの?……母の伝統を立てる前に息子の伝統を立てることができないことを知っているの?」(「選集」323-83、2000・5・31)
また、これらのみ言と共に「顧命性宣誓宣布」式についても、併せて確認しておく必要がある。「顧命」とは、「王の遺言」を意味する言葉である。この儀式は、真の父母様が1991年11月30日に北朝鮮を訪問される前に、その年の6月カナダで持たれた特別な宣布式である。その内容は、真のお父様が聖和されたときは真のお母様が後継であること、またその時には、真のお母様を母の国の日本が支えていかなければならないこと、などが真のお父様の命令として宣布されたものである(自叙伝『人類の涙をぬぐう平和の母』220頁参照)。
以上の内容を踏まえた上で、今一歩踏み込んだ形で「お母様の時代」に生きる意味を考えてみたいと思う。
(注1)ところで非原理的集団の問題を扱うに際し、若干理解しておかなければならないことがある。それは、分別思想(分立・聖別思想、義の論理)と博愛思想(愛の論理)との関係性であり、また両者の使い分けである。よく次のような意見が寄せられる。「そんなに分派、分派と言って分け隔てせず、皆神様の前に同じ兄弟姉妹として愛し合うべきではないか」と。確かにそれは間違っておらず、またそのとおりでもある。しかしそれは一つの暗黙の、あるいは無意識の前提(善悪分立摂理)の上に立っての話なのである。
すなわち、聖(善)なるものに悪(看過できない不正)なるものが混入した場合、いくら愛の神といえどもそのままでは相対できない――そのまま容認すれば神を中心とした真の秩序の立つ道が塞がれてしまう――。それは丁度、堕落したアダムに、神は無条件で相対できないのと同じである。その場合、神は先ず、善の表示体(以後アベル的存在と記す)と悪の表示体(以後カイン的存在と記す)に分け(善悪分立・分別・聖別摂理)、その上で神はアベル的存在を通してカイン的存在に働きかけようとされる――神は、堕落したアダム家庭全員を無条件で、無差別に容認し受け入れようとされるわけではない――。すなわち神は〝善悪分立摂理の基台の上〟で、アベル的存在を通して愛のみ手(真の愛・アガペーの愛・博愛)を惜しみなく、カイン的存在に施されようとされるのであり、またそのことを通して、カイン的存在が――神の愛の御前に自然屈伏することにより――神の下に帰って来られる道を用意されるのである。
すなわち、先ず非原理的、分派的な考え方に対し、どこが問題であるかを見極め、明確にすることが善悪分立摂理であり、その「基台」(前提)の上に立って――時にそれを心に秘め――、そのような考え方の人たちが神の下に帰って来られるよう、真の愛をもって対応することがアベル的存在の使命であると言うことができるであろう。
2 ユダヤ・キリスト教的観点との対比で考える
ところで、筆者はキリスト教の信仰を持つ立場から家庭連合に導かれ、また家庭連合でもキリスト教界の渉外を担当する部門に長くいたこともあって、キリスト教について学ぶ機会が多くあった。そのような関係上、家庭連合のいろいろな問題も、キリスト教的観点――正確にはユダヤ・キリスト教的観点――と対比して考えると理解しやすい、と思われることが多くある。そこで本稿ではそのような観点に立ちつつ、基本的な話から始め、徐々に問題の核心へ話を進めていきたいと思う。
――ただし、そのような回りくどいことは嫌だと思われる方は、これ以降の項目を飛ばし、項目「8 ユダヤ・キリスト教から学ぶ啓示理解」辺りから読んでいただいても結構である――。
さて、ところで、キリスト教信仰にはファンダメンタルとリベラルという対概念がある。これは一般社会でも使われている概念であるが、キリスト教信仰においてはどのような意味を持つのか、ということになれば若干不慣れな方もおられるかもしれない。そこで本論に入っていく序論的意味合いも込め、キリスト教信仰におけるこの対概念について簡単に触れておきたいと思う。
3 キリスト教信仰の特質 ――ファンダメンタルとリベラル――
すなわち、ファンダメンタルとリベラルは、キリスト教信仰における特質を表す対概念であるが、端的に言って、ファンダメンタル(根本主義的)とは、聖書の言葉を――少々非科学的また非現実的であっても――そのまま一言一句神の言葉(啓示)として信じ、受け入れようとする信仰的傾向を指す言葉である。このような信仰観を持つ人たちは、そこに書かれている奇跡物語など(イエスの処女降誕、肉体の復活など)をそのまま信じると共に、また一方では人間の堕罪や十字架の贖罪による救い(福音主義)といった伝統的な教理的側面を強調しようとする。しかし他方、それ故聖書の言葉(文字)にとらわれ、現実と遊離した考え方をしたり、またその背後の真意(神意)を読み取り損ねる恐れを持っている、とも言える。
また、リベラル(自由主義的)とは、聖書の言葉をそのまま神の言葉(啓示)として受け入れようとするのではなく、出来るだけ理性的現実的に納得できるよう解釈し、受け入れようとする信仰的傾向を指す言葉である。このような信仰観を持つ人たちは、そこに書かれている奇跡物語などは神話だとし、原罪や十字架の贖罪による救いといった教理的側面よりも、道徳的倫理的側面を強調しようとする。しかしそれ故また、理性を優先する結果、聖書の中の啓示的(霊的)なメッセージを見落としてしまう恐れを持っているとも言える。
ところで、現代のキリスト教(特にプロテスタント)は、極端にファンダメンタルな信仰を持つ人たちや、反対に極端にリベラルな信仰を持つ人たちはどちらかと言えば少数派で、その多くは、中庸的立場の――すなわち聖書の啓示性を認めつつも、一方では理性的現実的理解も受け入れようとする――、多種多様な信仰観を持つ人たちによって占められていると言えよう。
ところで、実は、今日に見るこのようなキリスト教信仰の特質は、それなりの歴史的背景をもって生まれてきたものである。そこで、――後々の議論にも必要になるので――、少し遠回りになるが、以下、それらが形成されてきた経緯を概観しておきたいと思う。
4 近代キリスト教と聖書批評学
16世紀、ルターやカルヴァンの宗教改革によって始まったキリスト教プロテスタント信仰(正統主義的信仰)は、教会における絶対的権威を教皇から聖書に移すことをもって始まった。そういう意味ではプロテスタントの出発は、まさしく聖書の権威を第一とするファンダメンタルな信仰の源流としての出発であった。しかしながら18世紀に入り、この流れは大きな試練に遭遇することになる。それが聖書批評学の台頭である。すなわち近代における啓蒙主義の勃興と共に、それまで無批判に信じられてきた事柄に理性的実証的(科学的)検証の目が向けられるようになったが、そのような試みが聖書にも向けられたのが聖書批評学(Biblical Criticism)である。その結果、それまで一言一句が神の言と信じられてきた聖書の記述の中に、神の言(啓示)とは信じ難い多くの矛盾性のあることが、指摘されるようになったのである。
例えばどういうことなのか、以下にその一部を紹介してみたい。
1)聖書中に記述のくい違いがある
(1)旧約聖書における記述の問題
創世記1章の天地創造の物語と2章の天地創造の物語の間にくい違いがある。1章では人間が造られる前に植物や動物が造られたことになっているが、2章では人間が造られた後にそれらが造られたことになっている。またヘブル語の原典を見ると1章では神には「エロヒーム」という単語が使われているが、2章では「ヤハウェ」という単語が使われている。また文書表現(文体)という観点から見ても違いがあり、1章は技巧的で荘重な文体で書かれ、そこでの神は姿が見えず威厳のある声だけが聞こえている。しかし2章は素朴で写実的な文体で書かれ、そこでの神は擬人化されており、土でものを造り、それを人間のところに持って(連れて)来たりする神である。
創世記のこのような矛盾点を最初に指摘したのは、フランスのジャン・アストリュック(1684~1766)であった。彼は、創世記が一人の人物(当時信じられていたのはモーセ)により書かれたとするなら、このようなことはありえないとして、創世記は神をエロヒームと呼ぶ資料と、ヤハウェと呼ぶ資料の二つを使い、編集されたものであると主張した。その後この種の研究が進められた結果、そのようなことがモーセ五書(創世記から申命記)全体に言えることが分かった。そして最終的にモーセ五書は、少なくとも異なる時代に異なる人物(たち)により書かれた4つの資料(JEDPの四資料)を元に、後の時代に編集されたものであることが分かってきたのである。これがいわゆるグラーフ・ヴェルハウゼン学説で、その後多少の異論が出されているが、今日神学界では広く認められている学説となっている(注2)。
(2)新約聖書における記述の問題
①イエスと弟子たちの最後の晩餐の日が、共観福音書(マタイ・マルコ・ルカ)では過越の食事の日になっているが(マルコ14・12~16)、ヨハネ伝では過越の食事の日の前日になっている(ヨハネ13・1、18・28)。
②イエスを裏切った弟子ユダは、マタイ伝では首を吊って死んだことになっているが(マタイ27・5)、使徒行伝では自分の得た土地にまっさかさまに落ち、腹が裂け死んだことになっている(使徒行伝1・18)。
③イエスは復活の後、最初に弟子たちに会ったのは、マタイ伝ではガリラヤの山の上となっているが(マタイ28・16~17)、ヨハネ伝ではエルサレムの閉ざされた家の中となっている(ヨハネ20・19)。
2)聖書の記述と史実の間にくい違いがある
聖書では、ネブカデネザルがエルサレムを攻めるため来たのは、ユダヤの王エホヤキムの治世の第3年(ダニエル1・1)となっているが、実際はユダヤの王エホヤキンが即位した3ヶ月後である。また聖書にはベルシャザルの父はネブカデネザル(ダニエル5・2)となっているが、実際はベルシャザルの父はナボニダスである。
3)聖書の記述と自然界の事実の間にくい違いがある
聖書では、岩たぬきも野うさぎも反芻することになっているが(レビ記11・5~6)、実際は両者共反芻しない(岩たぬきの消化器は特殊構造をしており、また両者は物を食べるとき口をもぐもぐさせるので一見反芻するように見える)。
(注2)詳しくは拙著『やさしい聖書学』(光言社)67頁以下を参照されたい。
5 自由主義神学の台頭
さて、このようにして台頭してきた聖書批評学は、当時の合理主義的潮流を背景に大きく進展し、ついにドイツの神学者ライマールス(1694~1768)をして「あの奇跡物語を本気で書いた新約聖書の作者たちは敬虔な詐欺師である」(ケァンズ著『基督教全史』551頁)、とまで言わしめるに至った。その結果、それまで神の言葉と信じられてきた聖書や、その上に立っていた教会の権威が著しく失墜することとなり、遂に当時のキリスト教は知識層の大部分から見放される状態となったのである(ホーダーン著『現代キリスト教神学入門』以下『神学入門』と略す。77頁参照)。
ところで、19世紀になって、このような時代的攻勢に対して、それを克服し新たなキリスト教の未来を切り開こうする人たちが出てきた。これらの人たちの考え方は、聖書の文字や教理に囚われてきたそれまでの考え方からの自由を唱えるところから自由主義神学(Liberal theology)と呼ばれる(注3)。
自由主義神学の最初の道を開いたのは、シュライエルマッハー(1768~1834)である。彼は、合理主義や聖書批評学の攻撃を避けるため、聖書の文字や教理に囚われてきたそれまでのキリスト教に対し、「情緒」を中心としたキリスト教を主張して当時の宗教界に大きな影響を与えた(『神学入門』77頁参照)。彼によれば、聖書を神の言葉(啓示)と信じるかどうかとか、人間始祖の堕罪やキリストの十字架による贖罪を信じるかどうか、ということがキリスト教信仰の本質ではなく、神と人とを包括する情緒、すなわち「絶対依存感情」こそが、それであるというのである(小田垣雅也著『キリスト教の歴史』196頁参照)。
続いて19世紀後半になって、偉大な実践的神学者といわれるリッチュル(1822~1889)が登場してきた。彼は、宗教は「主として知識にかかわるものではなく、むしろ人間の実践的倫理的努力にかかわるものである」(『キリスト教大事典』教文館1131頁)として、原罪説や法廷論的な贖罪思想を退けた。
そして、このリッチュルの後を受けて出てきたのがハルナック(1851~1930)である。彼は、「イエスの単純な福音を、まことに手のこんだ神学へと変質させてしまったのは、パウロ」(『神学入門』84頁)であり、また後期ギリシャ哲学思想(ヨハネ伝)であるとして、「イエスに関する信仰」ではなく、「イエスの信仰」に帰るべきだと主張した。彼のイエスに絞った分かりやすい福音理解は、当時の人たちから歓迎され、彼の著書『キリスト教の本質』は、長い間ベストセラーの位置を維持し続けた(ウィキペディア・「アドルフ・フォン・ハルナック」の項)。
このような人たちにより主導された自由主義神学は――まさしくリベラルなキリスト教信仰の源流となったものであるが――、以下のような特徴を持ち、当時の合理主義や聖書批評学からの攻勢を超克する一つの道を示すものであった。すなわち、1)聖書を神の啓示の書と認めず、人により書かれた宗教書と見る。2)原罪や十字架による贖罪の教理を認めず、人々を倫理的道徳的関心に向かわせる。3)イエスは神ではなく理想的な人間、「道徳の教師」(『神学入門』147頁)とする。4)処女降誕やイエスの復活などの奇跡を否定する、などである。
このように自由主義神学は、極めて楽観主義的傾向を持つものであったため、18世紀の合理主義から19世紀のロマン主義に移ってきた当時の時代的潮流とあいまって、当時の人々から大いに歓迎された。そしてついにこの流れは、正統主義的キリスト教に取って代わり主流的流れとなったのである。彼らのモットーは「神こそ父であり、人々は皆兄弟」(『神学入門』126頁)であり、彼らによれば、まさにその延長上に「神の下の人類一家族の理想世界」、イエスの説いた「神の国」(地上天国)が来るはずであったのである(『神学入門』192頁)。
(注3)このような動きは、既に17世紀後半から18世紀にかけて哲学や宗教学的分野で始まっていたが、その代表的なものが「理神論」である。
6 自由主義神学の挫折
しかしながら20世紀に入り、自由主義神学の流れは大きな挫折を経験する。それは二度にわたる世界大戦から来る挫折であった。人間の理性と善意に絶対的信頼を置き、「神こそ父であり、人々は皆兄弟」という旗印の下、希望の未来を見つめて歩んでいた彼らに待っていたのは、文明国といわれる国々が二度にわたり互いに戦い、殺しあうという混乱の世界であった。そのような現実に対し、自由主義神学は説明する言葉を持たず、急速に衰退していった(『神学入門』192頁参照)。
そして人々は、それら大戦の背後に、人類の根底に潜む悪なるものの存在(罪・原罪)を認めざるを得なかったのである。それは、いわば人類史的次元での原罪体験(再発見)であった。彼らは改めて、「正統主義に何か真理契機があるにちがいないとの問いを発せざるをえなかった」(『神学入門』146頁)のである。すなわち、人間は、罪を宿命的におわされているのではないのか、人間の生きる道は、これだと示されるだけで解決されるような安易なものではない――善を求めてもそれを為しえない現実(人間の弱さとでも言うべきもの)が存在する(パウロの嘆き=ロマ書7・18)――。それは、むしろ魂の根底から新しくされなければ(ヨハネ3・3)行くことが出来ない道である。もしそうならイエスに対する期待は、単なる道徳の教師以上のものでなければならないはずである。すなわち罪から解放してくれる人こそ、われわれが必要とする人ではないのか、と(『神学入門』147、159頁参照)。
しかしながら、そうだからといってそのまま元の正統主義的神学に戻れない。なぜならば、そこには合理主義や聖書批評学からの攻撃が待っているからである。
19世紀になり自由主義神学に乗って大きな流れをつくってきた近代キリスト教は、20世紀に入り、前にも進めなければ後にも戻れない危機的状況に追い込まれてしまったのであった。
7 新正統主義神学の勃興
そのような状況下、20世紀になってその混沌を一気に吹き飛ばし、ある意味今日まで続く新しいキリスト教復興の道を開いたのが新正統主義(Neo-Orthodoxy)と呼ばれるまさに画期的な神学的信仰復興運動であった。再臨時代を準備したとも言えるこの運動は、カール・バルト(1886~1968)やエミール・ブルンナー(1889~1966)などにより始められたが、その最初の一撃は1919年に発刊されたバルトの『ロマ書講解』であった(『神学入門』191頁参照)。
実はこの神学的運動は、キルケゴールに始まる実存主義的考え方を基層とするもので、それまでの合理主義的観念論的考え方(自由主義神学)と異なり、二者間(主体と客体)の実存的出合いと、それにより新しく生じる(生起する)事柄にリアリティーを見ようとするものである(『神学入門』180頁参照)――この考え方はある意味で「統一原理」の「正分合作用」に通じる概念ともいえる――。
新正統主義は、このような観点に立って、人々があっと驚くような〝新しい啓示理解の道〟を示したのであった。すなわち、その考えによれば聖書は、啓示の書ではなく、啓示について証言された人間の書である。したがってそこには様々な限界や矛盾性が存在するのは当然といえる。それ故われわれは、それら(証言・聖書)を通して啓示そのものに出合わなければならない。そして、その啓示そのものとの実存的な出合いを通して人は救われる(=救いという事柄が生起する)、というのである。では、啓示そのものとは何かといえば、それこそイエス・キリストであるというのである(注4)。それは、まさしく「わたしを見た者は、父を見たのである」(ヨハネ14・9)という聖句によって要約されているものといえる(注5)。
このようにして新正統主義神学は、合理主義や聖書批評学からの聖書への攻撃を克服しただけでなく、それらをある意味で積極的に活用しながら、聖書の記述の背後にある啓示的本質をつかみ取る道を切り開いたのであった。
以後、活路を見出したキリスト教(プロテスタント)は、バルト一色とも言うべき状況(『神学入門』191~216頁参照)となり、カトリックにまで影響を与えつつ大きな信仰的復興期を迎えることになったのである。その後この運動は、多くの著名な神学者(ブルトマン、ニーバー、ティリッヒ、ボンヘッファーなど)により継承発展され、1960年前半まで続いた(『現代神学の最前線』栗林輝夫15頁参照)。それは、まさしく1920年から始まるキリスト再臨期の土壌を用意する摂理的運動であったと言えるであろう。
(注4)「神ご自身が人間に対してイエス・キリストにおいてすべてを啓示され、人間が神の啓示に出会う唯一の場所は、旧新約聖書である」(『20世紀のプロテスタント神学(上)』H・ツァールント74頁)
(注5)以下の聖句もこれに関連する。「あなたがたは、聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は、わたしについてあかしをするものである」(ヨハネ5・39)、「わたしは道であり、真理であり、命である」(ヨハネ14・6)。一方またバルトは、聖霊の介在により聖書の中の特定の言葉と実存的に出合うとき、その言葉はその人にとって神の言葉(啓示)となるというようなことも言っている。
8 ユダヤ・キリスト教から学ぶ啓示理解
1)啓示的資料の取り扱い方
以上、少し遠回りになったが、主に「神の啓示」(注6)とどう向き合ってきたかという観点から、近代キリスト教の歴史を概観してきた。ところで筆者はこの流れの中に、今日一部の食口が抱えているいくつかの問題を解くヒントが隠されているのではないかと考えている。
そのひとつに、共にメシヤとしての啓示的な言葉である真のお父様のみ言と真のお母様のみ言の間に、また時にはお父様のみ言とみ言の間にも、一見食い違いがあるように見えるという問題(注7)であり、またそれらをどのように捉えるべきかという問題である。
実はこのような問題は、同じように神の啓示的資料を扱ってきたユダヤ・キリスト教の歴史の中でも経験してきたことであった。早い話が聖書(正典)の成立(編纂)に関する問題がそうである。旧約聖書にしろ新約聖書にしろそれらは、書かれた年代や背景の異なる種々の啓示的資料(文書)が収集され、編集され出来上がったものである(注8)。したがって、すでにそれら資料が収集される段階で、それら資料には多くの矛盾性が内包される可能性があったのであり、実際あったのである。
このような場合、先人たちはどうしたかと言えば、むやみに手を加えることを避け――ある意味で矛盾したまま――それらを並列に収録しようとしたのであった。そこには、先人たちの理性よりも啓示を優先しようとする姿勢(=知恵)が読み取れる。例えば既に学んできた創世記の一章と二章の間にそれが見られる。そこでは、その成立の背景が異なる二つの資料(注9)から取られた一見すると内容が食い違う二つの天地創造物語が――無理に両者の整合性をとろうとはせず、文体や用語すら統一されないまま――並列された形で接合され、一つの文書として編集されている。このようなやり方は、まとまった文書を作るという観点から見れば一見乱暴のように見える。しかしそのお陰で今日われわれは、そこから損傷の少ない多くの重要な啓示的メッセージを得ることが出来るわけである。
このようなことは、聖書の各書物間にも言える。例えば新約聖書のロマ書では「信仰」が強調されているが、ヤコブ書では「行い」が強調されている。両者の間には一見論調の食い違いが見られる(注10)。しかしながら両者とも神の啓示の書として収録されたが故に、今日我々は信仰生活のあり方について、より幅広い観点からの示唆を得ることができるわけである。
これに類することは、キリスト教の歴史の中にも見られる。初期のキリスト教では三位一体論と共にキリスト論、すなわちキリストとは何かということが問題になった。聖書から読み取れるのは、キリストは人間であるということと共に、またキリストは神であるということである――ここでの神とは、単にキリストの中に神が宿っているということではなく、キリストそのものが人であると共に神であるということである――。この神と人という異質なものがどうして一存在としてありえるのか、この問題をかけて話し合われたのが451年のカルケドン公会議(注11)であった。その結果、論理的には説明不可能であるが「キリストは人間であると共に神であり、しかも一人格」という結論が採択されたのである。
すなわち、ここでも言わば一存在に対し論理的には説明できない二つの結論――キリストは神である。キリストは人である――が並列的に結合されており、理性よりも啓示を優先する形となっている。それ故、その後の神学者たちは今日まで、この説明に頭を悩まされてきたのであった(シーセン著『組織神学』503頁参照)。しかしながら再臨の時代になってこの難問は、以下に示すような「統一原理」的観点から見ることによって見事にその解決の道が示されたのであった。すなわち、そこにおいては完成した人間(キリスト)は、神の神性を百パーセント実体化した存在であり、本質的には神と同質であって、言うならば実体化した神なのである(注12)。そういう意味では、やはりキリストは人間であると共に神であり、しかも一人格という結論もある意味で正しかったのである(注13)。カルケドン公会議でのこの結論――ニケヤ公会議での結論(三位一体論)も含め、キリストを神と見る考え方――があったからこそ、今日まで二千年キリスト教が続いてこられたのだ、と筆者は思っている。
もちろん論理的整合性を求める作業は、可能な限りなされるべきである。しかしながら最終的に啓示と理性との折り合いが付かない場合、理性より啓示を優先してきた先人たちの姿勢や経験は、天一国時代に生きる我々にも多くの示唆を与えるものと言えよう。
(注6)本来神は目に見えず、耳に聞こえず、手に触れることができない存在であり、人間にとって直接認識することができない存在である。それ故人間が神を認識するには、神の方から人間に何らかの方法でご自身のことを表されなければならない。この神が何らかの方法でご自身のことを表されることを、キリスト教神学では啓示と呼ぶ。
(注7)なぜこのようなことが起こるのかと言えば、本来神の啓示は、それを受ける個体の状況、(心霊と知能のレベル、置かれている時代的環境的状況など)に合わせて与えられるものであり、決して客観的で論理的一貫性を持って――言わば神学論文的な形式で――与えられるものでないからといえる。このことは、『原理講論』第3章第5節(1)「終末と新しい真理」(168頁以下)にも論じられている。実はこのようなことは、今の時代の中においてもあり得ると筆者は考える。
(注8)聖書の成立の背景には、人為的な編集作業が介在したと考えるのが今日一般的な神学的見解である。しかしながらそのような作業の背後にも神のみ手があって、今日の聖書のあることもまた見逃されてはならない。
(注9)一章はBC5世紀ごろバビロン捕囚中またはその直後に成立したと見られるP資料から、二章はBC9世紀ごろ南朝ユダで成立したと見られるJ資料から取られたとされる。より詳しくは拙著『やさしい聖書学』(光言社)を参照されたい。
(注10)「人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるのである。」ロマ3・28)、「人が義とされるのは、行いによるのであって、信仰だけによるのではない」(ヤコブ2・24)
(注11)これ以前に神観、すなわち三位一体論を中心に話し合われたのが325年のニケヤ公会議である。
(注12)「彼の神性から見て彼を神ともいえる」(『原理講論』258頁)、「アダムとエバは……実体世界に現れた実体の神様である」(『文鮮明先生の日本語による御言集8』102頁)
(注13)この例に見るように、後世一層深い啓示理解の道が示される可能性については、真のお父様は、生前〝後世多くの学者たちが、先生のみ言を研究する時代が来る〟とも語られ、また今後霊界と地上界が完全に一体化し交流できる時代が来るとも語られた。天にはまだまだ多くの秘密が隠されていることも事実である。今は理解できなくても、後の時代になって明らかにされる事柄も多々あると思われる。
2)啓示の本体は言葉でなく「実体」
しかしながら、前述のような観点を展開していくと、では最終的にわれわれは何をもって絶対的な真理の基準(拠所)とすることができるのか、という問題が出てくる。実は、この問題に一つの解答として提示されたのが前述の新正統主義神学であった。そこでは、聖書の言葉(文字)そのものが啓示(真理)ではなく、それは啓示について証言されたものである。われわれはそれらを通して啓示そのもの(本体)、すなわちキリスト(実体)に出会うべきであり、それによって救われる、というものであった。言わばそこでは、コペルニクス的転回とも言える啓示理解の道が導入されているのであって、啓示の本体=絶対的な真理の基準を、それまでの「言葉」(文字・聖書)から「実体」(キリスト)に求める、というものである。
このような新正統主義神学が提起した啓示理解の道は、今日、ともすれば言葉そのものに捉われがちなわれわれにも、有用な示唆を与えるものと言える。
9 「統一原理」の啓示理解と真の父母
では、「統一原理」では、神の啓示についてどのように理解されているのであろうか。結論から言えば、前述の新正統主義神学が主張する啓示理解と近い内容が示されていると言えるであろう。われわれは、以下の真のお父様のみ言や、『原理講論』の記述からそれを確認することが出来る。
・「み言が先でしょうか、実体が先でしょうか。……統一教会では、み言が先ではありません。実体があって、その実体が行った事実をみ言で証するので、内外が一致し得る内容を知ることができるというのです」(『真の父母経』13-1-5-5、2010・7・8)
・「真理とは何であり、真理の根本とは何でしょうか。……一人の男性と一人の女性以外にはないのです。全世界の男性を代表する真の男性がいれば、その真の男性の四肢五体が真理です。真理は文字ではありません。真の男性と真の女性が真理なのです。……真の愛をもった真理体である真の真理の夫婦が一つになるとき、真の真理の殿堂になるのです」(「選集」182-81、1988・10・14、『絶対価値』25頁)
・「イエスは、そのみ言を真理と言わないで、彼自身がすなわち、道であり、真理であり、命であると言われたのであった(ヨハネ14・6)。……イエスのみ言はどこまでも真理であられる御自身を表現する一つの方法であるにすぎず……聖書の文字は……真理それ自体ではないということを、我々は知っていなければならない」(『原理講論』169頁)
ここで真のお父様が明確に述べられていることは、啓示の本体は、「み言」(文字)ではなく「実体」であること、またその実体とは何かと言うと「真の男性」と「真の女性」であり、またその両者が真の愛により一つになった「真の真理の夫婦」である、ということである。では、ここで言われている「真の真理の夫婦」とは何かと言えば、それはまさしく「統一原理」で言う「真の父母」に他ならない。したがって「真の父母」こそ啓示の実体であり、絶対的な真理の基準であるという結論が導き出されてくる。
ただし、だからと言ってみ言がおろそかにされて良いということではない。すなわち、実際、真理は実体であっても、一義的には、それを証しするみ言を通して、それを知りえるのである。それ故、実体とみ言は表裏一体(内外一体)の関係であって、共に一体として尊ばれなければならないことは言うまでもない。
10 絶対的価値を持つ「天宙の中心核」としての「真の父母」と人類の平和
さて、前項で真の父母は、啓示の実体であり、絶対的な真理の基準であることを確認したが、そのことはまた同時に真の父母は、天宙において原点的存在であり、中心ポイント的、中心核的存在である、ということを、われわれは以下のみ言から確認することができる。
・「『真の父母』という名が出てくることによって、神様の創造理想世界、エデンの園から出発すべきだった永遠の未来の天国が、ここから出発するのです。その事実は歴史的であり、時代的であり、未来的です。ですから……この地上に顕現した真の父母は、宇宙の中心を決定する中心ポイントです。歴史はここから実を結び、ここから収拾され、ここから出発するのです。……世界がここで一つの世界に収拾されるのであり……新しい天国が成就されるのです」(選集44-132、1971・5・6、『絶対価値』24頁)
・「天宙の中心になる核と柱である天地父母、真の父母……真の父母様の名で、地上と天上における一心一体となった実体の一つの中心、一つの核と一つの柱を中心として、永続的な天国理想を拡大し、守っていくことを願います」(『真の父母経』5-4-4-33、2011・2・3)
それ故にまた、真の父母は天宙において唯一的存在であり、他に真の父母という存在のありえないことも、以下のみ言から明らかである。
・「真の父母様は一組だけです。今、この時の一度だけだというのです。過去にもいなかったのであり、未来にもいません。真の父母様が肉身をもって実体で存在するのは、この時だけだというのです。永遠の中でたった一度です」(「選集」246-84、1993・3・23、『絶対価値』29頁)
・「真の父母が二組もいることができますか、絶対に一組です。先生が霊界に行けば終わりです。永遠に存在しません」(「選集」229-161、1992・4・11、『絶対価値』30頁)
なおここで言われている「永遠に存在しません」とは、真の父母様という存在が永遠に消えてなくなる、ということではない。すなわち、真の父母という存在は、未来永劫にわたって一組であり、唯一の存在であって、一旦聖和されたらその後は霊界において永存されるのであって、二度とこの地上に人類の「真の父母」という存在が現れることがない、という意味である。
ところで、これまで「家庭連合」では、真の父母の持つ意味(価値)を、どちらかと言えば救済論的立場から見ることが多かったが、前述してきた内容は、言わばそれを存在論的立場から見たものであり、ある意味、より本質論的な観点からの結論であるともいえる。それらをまとめてみると以下のようになる。
すなわち、真の父母という存在は、天宙における啓示の本体、真理の基準、原点的存在であって、未来永劫にわたり天宙における唯一の中心ポイント、中心核的存在であって、人類にとってまさに絶対的価値を持つ存在である(注14)。
そして、われわれ人類は、この真の父母という絶対的価値を持つ基点=原点的、中心核的存在を得て、初めて本当の意味で、一つになれる道、平和と幸福に至る道を歩み始めることができるのである。
しかしながら、一方では次のような声が寄せられるかもしれない。「そのような固い(観念的な)ことを言うから話がややこしくなるのである。もっと簡単に考えたらどうか、親である神を中心とし全人類一家族、『One Family Under God』、これだけで十分ではないか」と。確かにこの標語は、「家庭連合」の中でも常々使われており、間違ってはいない。また、実際一つの平和勢力を形成していく上において、有効な標語でもある。しかしながら、そこから一歩前に進もうとする時、そこに集まった人たちの神観、人間観、世界観などはまちまちであって、それだけで人類は、最終的に一つとなることはできない。すなわち、そのためには、神もサタン(天使)も全人類も、ひいては全万物までもが認めることのできる共通の――絶対、唯一、不変、永遠的価値を持つ――中心核が定められなければならない。その中心核が定まってこそ、初めて全人類がそれを中心として真に(永遠に)一つになれる道が開かれてくるのである。その中心核こそまさに「真の父母」なのである。
(注14)救済論的観点から見た真の父母の絶対的価値については後述する。
11 真の父母の「最終一体」と「定着」、及び「天地人真の父母定着実体み言宣布天宙大会」
さて、ところで、前述した天宙の中心核的存在としての「真の父母」の誕生は、1960年4月11日(天暦3月16日)に行われたいわゆる「小羊の婚姻」、すなわち真の父母様のご聖婚を通して現実のものとなったのであった。その日は、まさしく神にとっても、人類にとっても、万物にとっても待ちに待った一日であったのであり、慶事中の慶事であったのである。
しかしながら、このように顕現された真の父母様が、最終的に勝利された真の父母様として立たれるには、なおその後歩まれなければならない血と汗と涙の道があったことをわれわれは知っている。
では、真の父母様が、最終的に勝利されるとは如何なることを言うのであろうか。それは、まさに血と汗と涙の道を通し、真の父母として果たすべき復帰摂理的蕩減条件――人類のそれまでの罪を人類に代わって蕩減するための蕩減条件――をすべて勝利された基台の上で、神を中心として真の愛により「最終一体」を完了(実体的三位一体を完成)されることによって、なされると言えるであろう。
では、そのような意味での、真の父母の「最終一体」は、いつ(頃)成し遂げられたのであろうか。このことに関しては、以下のみ言にあるように、米国・ラスベガスにおいて2010年6月19日(天暦5月8日)と同年6月26日(天暦5月15日)の両日をもってなされた「真の父母様最終一体完成・完結・完了宣布」によって、われわれは、それが最終的に成し遂げられたことを知ることができる。
・「2010年天暦5月8日、午前2時20分と5月15日午前3時25分、このように両日にかけてアメリカのラスベガスにおいて、神様を中心とした天地人真の父母様の特別宣布が行われました。……既に真の父母様御夫妻は、最終一体を成し遂げ、完成、完結、完了の基準で、全体、全般、全権、全能の時代を奉献宣布されたのです」(天一国経典『天聖経』13-4-3-1)
ところで、ここで留意したいことは、このみ言の中で使われている「最終一体」という言葉である。その意味するところは、真の父母様が〝最終的〟に一体となられたということであり、したがって、その後如何なることがあっても両者は離れるということはないということである。それ故、また当然のことであるが、それ以後、両者の組み合わせの変更などということも、ありえないということである(注15)。
さて、ところで、真のお父様は、以下に引用しているみ言にあるように、真の父母様が「最終一体」を完成された直後から〝真の父母の定着〟という言葉を使われるようになった。そして定着の意味については「実体が定着したということです」と述べておられる。すなわち真の父母様が「最終一体」を完成されることにより、真の父母様が「定着」されたのであり、その定着とはまさに真の父母という「実体」(存在)そのものが定着されたということである(注16)。そのことは、とりもなおさず真の父母様が、最終的に、――これまで本稿で論じてきたように――絶対的な〝真理の基準としての実体〟となられたことを意味するものであり、同時に真の父母様の最終的で決定的な勝利を意味するものでもある、といえよう。
それ故、このようにして成し遂げられた真の父母様の〝最終的で決定的な勝利〟と、その勝利された実体から発せられ、証しせられた〝総括的なみ言〟(注17)を天宙的に宣布するためになされたのが「天地人真の父母定着実体み言宣布天宙大会」であったのである。以下がこの宣布大会に関するお父様のみ言である。
・「天地人真の父母が定着しました。そのため、実体み言を宣布しなければなりません。真理の実体、定着した実体が語る言葉が、宇宙を解放できるのです。それが実体み言宣布です。天地人真の父母が定着したというのは、実体が定着したということです。ですから、実体み言宣布なのです。」(『真の父母経』13-1-5-7、2011・11・27)
・「私がきょう皆様に宣布するみ言は、真の父母様の生涯におけるすべての復帰摂理歴史の最終終結と完成を宣布するためのものです」(天一国経典『天聖経』13-4-1-1)
・「『天地人真の父母定着実体み言宣布天宙大会』は、み言を宣布する大会ですが、み言の前に実体をもってきました。個人から天地を連結させ、最終的な内容が完結するものとして、天地人真の父母定着と実体み言宣布と天宙大会があってこそ終わるのです」(『真の父母経』13-1-5-6、2011・4・3)
なお、ここでも留意しておきたいのは、真のお父様も言及されているように、この大会の名称に「み言実体」でなく、「実体」という言葉が先に置かれた「実体み言」という言葉が使われていることである。この両者には決定的な違いがある。「み言実体」宣布大会とすれば、真の父母がみ言の実体になられたことを宣布する大会とも捉えられる恐れがある。しかし、この大会はそうではなく、ここでのみ言から分かるように、真の父母という実体(存在)そのものが「定着」し〝真理の実体〟となられたことと、その実体の語るみ言を宣布する大会であったため、このような言葉が使われているのである。
そのようなわけでこの大会は、真の父母様の最終的勝利(実体定着)と総決算的み言を宣布するための大会であったため、真の父母様の「最終一体」が宣布された直後(12日後)の2010年7月8日に最初の大会が天正宮博物館で行われ、その後二年間(2010年~2011年)にわたって全世界的な規模で実施されたのであった。
ところでこの一連の大会は、ラスベガスに「本体論修練会」参加のため世界から集まって来ていた食口たちを対象にしても行われた(2011年5月21日、アリアホテル)。その時、真のお父様は、ご自身の講演用の原稿(大きな文字で印刷されたもの)をそのままコピーして作られたファイルを全参加者に記念品としてくださったが、このようなことからもこの大会が真の父母様の生涯において如何に決定的な意味を持つ大会であったかが分かる。
その後真のお父様は、2012年4月14日、米国・ラスベガスにおいて「特別宣布式」を挙行され、以下のように祈られて一連の大会を締めくくられた。
「天地人真の父母定着実体み言宣布天宙大会を最終完成・完結することを、お父様の前に奉献します」(『トゥデイズ・ワールドジャパン』2012年天暦4月号19頁)。
それから4か月後、同年8月13日、真のお父様は「すべて成し遂げました」(天一国経典『天聖経』「真の父母様の祈祷」13-8)と祈られ、同年9月3日(天暦7月17日)に聖和された。
(注15)したがって、「最終一体」宣布以後の真の父母様を中心とした様々な事象は、すべて「最終一体」の基台上での事象であり、われわれは、それらの中に「最終一体」を完成された真の父母様の位相を拝しつつ、歩むべきなのである。
しかしながら、一部の人たちは、真のお母様の言動を恣意的に解釈し、問題として、真のお母様の代わりに他の女性を立てる動きを示しているが、ありえないことである。彼らは、真のお父様がなされた祝福は、人に対するものではなく、位置に対するものなので、人を入れ替えてもその祝福の基台は崩れないと言っている。しかしそのようなことは、以下のような理由からも受け入れられない。すなわち、①真の母を入れ替える権限は真の子女といえども与えられていない。②本項目「11 真の父母の『最終一体』と『定着』、及び『天地人真の父母定着実体み言宣布天宙大会』」の後半に引用しているみ言や、論じている内容から明らかなように、真の父母の「最終一体」に基づく「定着」という概念は、単なる「位置」に対する概念ではなく、あくまで「実体」に対する概念――すなわち、実体が定着したということ――である。したがって実体が変更されても位置に対する祝福の基台が残っている、というような論理は意味をなさない。実体が変更されれば即勝利された真の父母の位相が崩れてしまうのである。③真のお父様は「すべて成し遂げました」(天一国経典『天聖経』「真の父母様の祈祷」13-8)と祈られ聖和された。このことは、真のお父様と真のお母様による最終的勝利を、肯定され聖和されたことを意味している。
(注16)ここで使われている「定着」という言葉は、カメラのフィルムに写し出された映像が、現像液に浸けられることによりフィルム上に浮かび上がり、その後定着液に浸けられることにより定着し、もはや如何なる強い光を当てても変化しなくなることを連想させる。すなわちここでの定着という意味は、真の父母という存在が永遠に不変的存在となられたことを意味するものといえる。
(注17)「『天地人真の父母定着実体み言宣布大会』で語ったみ言を、父母様の生涯路程全体を中心とする教材教本を代表するみ言として宣布します」(『真の父母経』5-4-5-32)。なお、講演の全文は天一国経典『天聖経』13篇4章に収録されている。
12 定着された真の父母と「天一国」
さて、以上見てきたように「天地人真の父母定着実体み言宣布天宙大会」は、真の父母の最終的勝利を天宙の前に宣布する大会であったが、それはまた同時に前述したごとく(項目「10」参照)、真の父母様が天宙史上初めて神も、サタン(天使)も、全人類も、全万物までもが認めうる絶対、唯一、不変、永遠的な中心核的存在となられたこと、を意味するものでもあったのである。その意味するところはあまりにも大きい。なぜなら、そのことによって人類は、初めて一つになれる道(平和の道)を得たのであり、また真の意味で歴史を出発できる原点(基点)を得たことになるからである。
事実、この最終的に勝利された真の父母様を中心核とし、原点として、――一連の大会の最終完結を宣布された翌年――、2013年天暦1月13日(陽暦同年2月22日)、基元節の日を期して「天一国」の実体的出発がなされたのであった。
それ故「天一国」は、天宙の絶対、唯一、不変、永遠的中心核となられた真の父母様を中心とし、原点として出発したのであるから、今後如何なることがあっても、真の父母様(天地人真の父母様)を中心として行くところ、「天一国」もまた絶対、唯一、不変、永遠的な輝きをもって存続していくことになるであろう。
・「これをもって……天地が昼夜もなく、神様の統治のもとに天地人真の父母様の支援を受けて永遠に存続するようになります。……神様と真の父母様を中心とした勝利圏の太平聖代だけが永遠に続くようになるでしょう」(天一国経典『天聖経』13-4-3-2~4)
13 「真のお母様の時代」に生きる
このようにして、「天一国」は基元節をもって実質的に出発したのであるが、真のお父様におかれては基元節を待たずして聖和された――そこには人知を超えた深い神意があったと思われる――。
それゆえ基元節の式典は、真の父母様を代表して真のお母様により執り行われた(注18)。このことは、まさしく地上での摂理が、真のお父様から真のお母様に引き継がれたことを意味するものであり、また同時に新しい摂理的時代である「真のお母様の時代」の到来を告げるものでもあったのである。
その後真のお母様は、3年間にわたる侍墓生活の精誠を捧げられ、以後「行く道がどれほど困難でも、私の代で復帰摂理を終わらせます」(『人類の涙をぬぐう平和の母』114頁)との固い決意のもと、復帰摂理の最前線に立たれ、今日まで奇跡的な働きをされておられることは、読者のよく知るところである。
それ故、今や、われわれは「真のお母様の時代」に生きる者として、最終的に勝利され、天宙の絶対、唯一、不変、永遠的な中心核的存在(定着実体)となられた真の父母様と、また地上においてはその代身として「天一国」建設に〝実践躬行〟される真のお母様と、如何に一つになって歩み得るかが〝まさに〟問われているのである。
真のお母様は、真の父母様と共に歩むこの期間を「黄金期」と言われている。ある意味〝最終的な復帰の峠〟を越えて行かんとするこの時(注19)、過ぎ去ってしまえば二度と来ないこの「黄金期」を、悔いのない歩みとすることが、今や家庭連合に属する食口一人ひとりに切に願われていると言えよう。
(注18)もちろんこの式典は、真のお父様が霊界から参加されることにより、実質的には真の父母により執り行われたといえる。このことに関しては、式典の中継を、ネットを通し見ていた横井保典氏(1800双)の以下の証言が参考になる。「天一国基元節の式典でのことは忘れられません。……映像で見る会場はまばゆいばかりに光り輝いていて、無数の天使が頌栄を捧げていました。その中を、五十代の若いお姿のお父様が、お母様と共に入場されるのが見えたのです。おふたりは、金の光を放つ聖杖を一緒に持っておられました」(『真のお母様、感謝します』69~70頁、光言社)。
(注19)であればこそ、時を知るサタンは最後の攻撃「発悪」を加えてきているのであるが。
* * *
以上をもって、おおよそ筆者の思っている中心的な内容を言い終えたつもりである。
しかしながら、筆者にはもう少し補足しておきたいと思ういくつかの事柄が残っている。それらは、これまでの議論を補強すると共に、また一方それらを実践に移す方向を提示しようとするものである。
したがってまた、時間的に余裕がないと思われる読者は、以下の項目を飛ばし、本稿の最終的な締めくくりとしての項目「16、17」に進んでいただいても結構である。
14「真のお母様の時代」にまつわる霊現象について
1)霊現象を見極める
『原理講論』には、霊現象には善神の業と悪神の業があると記されている。そしてこの両者を見極め、悪神の業を退け善神の業の協助を得て、自己の信仰を高めていくことが奨められている。
ところで、「真のお母様の時代」の到来と共に、その過渡的状況の中で、食口たちの信仰を混乱させるような一連の霊界からのメッセージとされるものがネット上に横行した。その中には草創期の大先輩や神学的権威とされた人たちの霊からというものや、ずばり真のお父様からというものまであった。しかもそれらを読んでみると、いかにもその人からのものと思われるような内容や口調で書かれていた(注20)。
筆者も事が事だけに、それらの真偽を確かめるべく慎重にその内容を分析、検討してみた。その結果気付いたことは、それらの殆どは、いずれも家庭連合を全面的に否定せず、ある意味で肯定する姿勢をみせながらも、――時に、お父様への信仰を強調する形において――最終的にわれわれの心を、真のお母様から巧妙にそらすものであり、また、そのようにしようとする背後の意図が感じられるものである、ということであった。すなわち、それらは結果的に、実体として定着され、勝利された真の父母様の位相を貶め、希薄化させようとするものであり、それ故、天の摂理的方向と相容れないものである。このように考えた筆者は、最終的に、それらは神から来たものではなく、また神の願う方向でもないと判断した。
たぶんそれらは、いわゆる偽造されたもの(フェイク)ではなく――そうかもしれないが――、確かに霊界から受け取ったメッセージであり、またそれを受けた食口も特別な意図を持っていなかったかもしれない。しかし、霊現象については、本項の冒頭で言及したように、それが善神の業か悪神の業かを慎重に見極められなければならない。聖書にも以下のように記されている。「驚くには及ばない。サタンも光の天使に擬装するのだから」(第二コリント11・14)(注21)。
事実、この聖句が示すように、悪霊がわれわれを〝騙す存在〟であることについては、サンダー・シング(1889~1929)(注22)も次のように言い、その危険性を指摘している。「交霊術者が交わる者(霊)は之らの低い霊界の者である。交霊術者等は彼らから面白い報知を得る。然し遂には彼らに欺かれてしまうのである。始め百中の九十九は真の事を語り一の偽を語るが、次第に度を進めて来て次には人々を無神論か又は他の悪い方向へ導いてしまうのである」(『サンダー・シング全集』153頁・金井為一郎著訳・基督教文書伝道会・丸括弧内引用者注)。また、スウェデンボルグもこれに関連して興味深いことを述べている。すなわち彼の言うには、霊界においてすら、霊界にいる霊人が他の霊人に騙されたり、誤ったビジョン(映像・風景)を見せられたりするというのである(注23)。したがって、もしこのようなことがあるとするならば、極端な話、単に霊界からのメッセージを受け取るという形だけではなく、本人が霊界に行って直接いろいろ見て来たという人の話であったとしても、それだけで信じることは危険だということである(注24)。
(注20)真のお母様は、それらの動きに注意するよう言及されたことがあったが―。
(注21)実際、悪霊が擬装するという問題については、筆者も直接経験したことがある。筆者が関西方面で伝道活動に携わっていたときのことである。一人の女性食口に霊が入り、いきなり男の声で「私は文鮮明である。この女はいい女である。皆この女の言うことを信じろ」というようなことを言い出したのであった。その口調はまさに真のお父様そっくりで、筆者もすぐさま本当のお父様か、偽者かの判断がつかず、恐る恐るその食口の話を聞いていた。しかし、そのうちその霊が調子に乗り「この女が素晴らしいので『子女の日』をこの女にやろうと思っている」とまで言い出したのである。ここまで来ると筆者もそんなことはありえないと考え、これは真のお父様ではないと確信して「お前は偽者だ」と叫んだのであった。するとがらりとその場の雰囲気が変わり背後の霊が出てきた。そこで「お前は何者なのか、何故この女に取り憑いたのか」などと聞いたらすらすらと答え出したのである。そこで筆者も思わず「そんなに霊というのは、他の人そっくりのまねが出来るのか」と聞いてみたら、その霊がはっきり「出来る」と言ったのには驚いてしまったことがある。
(注22)スウェデンボルグと同じように入神し、霊界と自由に交流したことで有名なインドのキリスト教伝道者。
(注23)『エマニュエル・スウェデンボルグの霊界Ⅱ――人間は、霊界に支配されている――』E.スウェデンボルグ著、今村光一抄訳・編集、70~72頁参照、中央アート出版社。
(注24)すなわち霊界に行って来たというその人ですら、霊界でだまされて帰って来ている可能性があるということである。例えばある霊能者が霊界に行って、ありえない真のお父様の姿を見て来たなどと語ることがあるが、そのような場合がこれに当たる。
2)善神の業
前述したのは、「真のお母様の時代」にまつわる霊現象の内、主に悪神の業について警鐘的意味を込め述べたものである。しかし、もちろん善神の業と思われる証も多数存在する。その中でも筆者が身近な所で得たいくつかの例を紹介しておきたい。
そのひとつは、ある祝福家庭のN夫人(777双)の証である。真のお父様が聖和された4年後の2016年、真のお母様は韓国でクリスマス集会を主催されたが、その折お母様はそこに招かれていた日本の幹部や、先輩家庭の人たちを集められ特別集会を持たれたことがあった。
実はその時、N夫人も先輩家庭の一員としてその場に参加しておられたのである。ところでN夫人の話によれば、集会が終わってお母様がその場を去ろうとされていたとき、お母様の後ろに大きなお父様が霊的に現れ、見ていると少しずつ姿が小さくなられ、お母様と同じ大きさになられた瞬間お母様の中に入られたという。そうしたら天井からきらきら輝く黄金の光の粒が降ってきたとのことで、その時N夫人は、お父様とお母様は一体となって歩んでおられること、また天井から降ってきた光の粒は神様だと感じたというのである。
また、これは筆者が直接本人から聞いた話であるが、ある祝福家庭(1800双)のS夫人の証である。この夫人はもともと霊的な恩恵を多く受けておられた方であるが、この夫人も真のお父様が聖和された後、真のお母様の時代になっていろいろ戸惑いを感じておられたそうである。そこで最終的に清平の天心苑で談判祈祷をされたところ、そこにお父様が霊的に現れ「お前の気持ちは分かる。しかし今お母様は大変な時なのだ。お母様を助けてほしい」という趣旨のみ言をいただいたという。
そのほかにも以下のような話もある。ある霊的な女性食口の話では、真のお父様の聖和後真のお母様が集会をされる時、初めのころは真の父母様用に二つの椅子が用意されていた。しかしあるときから一つの椅子だけ用意されるようになった。そのような時、霊眼で見るとお父様はお母様の中に入って、一緒に集会に参加しておられるのが見えるという。ただこの食口の話では、お母様が司式される祝福式のときは、お父様はお母様の横に並んで司式されている、とのことである。
これらの他にもいろいろな方面からの証(注25)が聞こえてくるが、特に最近は霊的な二世からの証しも増えてきているように思われる。それらいずれもが真のお父様は、今日に至るまで真のお母様と一体となって歩まれていることを証しするものである。
(注25)このような証しもある。数年前霊肉祝福を受けたある霊的な女性食口の話であるが、所属する教会の責任者に霊肉祝福の式典参加を申し込んだところ、その直後の夜、霊的にあるひとりの僧侶が現れ、自分の名前まで言って「自分はあなたの祝福相手として選ばれた者である」と言ったという――その食口はその僧侶の名前を知らなかったが、後で調べてみると歴史に名前が残っている古代の高僧のひとりであることが分かったとのことである――。その時その食口は「誰が決めてくれたのですか」と聞いたら、その僧侶は「真のお父様が決めてくれた」と言ったという。
その後その食口が真のお母様主管の祝福式に参加したところ、まさにその僧侶が現れ共に霊肉祝福を受けることができたとのことで、その後もその僧侶はいつもその食口と共にいて、共にみ旨を歩んでいるとのことである。このような証しも真のお父様は、真のお母様と共に働いておられることを証しするものといえる。
また、趣をことにするがこのような証しもある。筆者の信仰の友人で毎日のように霊的恩恵を受けているN氏(777双)の証しである。筆者は彼に直接次のように聞いてみたことがある。「お母様のみ言とお父様のみ言との関連性について霊界から何らかの言及がありましたか」と。すると彼が言うには、次のような趣旨のメッセージを貰ったことがあるとのことであった。すなわち、――読者はどう思われるか判らないが、筆者には大変興味深く思われたのであるが――、「お父様にはお父様としての責任分担があり、お母様にはお母様としての責任分担がある、両者の責任分担には違いがある。真のお母様は地上に現れた初めての母であり、今でも神は、真のお母様の一挙手一投足を新鮮な目で見つめている」と。
なお、以上の他にもう一件付け加えておきたい。実はこれは、本稿を一旦書き終えた後に入ってきたものであるが、2023年6月17日開催された孝情天寶特別映像修練会で李基誠苑長が語られた内容である。
すなわち、同苑長によると、今年6月始めごろ一人の牧師が、真のお母様に会いたいと天正宮博物館のゲートにやって来た。この牧師は、英国留学暦もあるエリートの牧師で次のように語ったという。「ある日、夢にものすごく光り輝く男女が現れ、誰なのか尋ねると『真の父母だ、私に従いなさい』と言われた。三日連続同じ夢を見たが、真の父母が異端で名高い家庭連合の教主であることを知り、自分はキリスト教の牧師であり従えないと断った。すると突然全身に湿疹が現れ、痒くて耐えられない日が続いた。それでついに受け入れると祈祷するとさっと湿疹が治った。それで約束どおり真の父母に会いに来たのだ」。
以上のような証しも、また最終的に真のお父様が真のお母様と一体となって歩んでおられることを証しするものであると言えるであろう。
15 復帰摂理から見た「真の父母」の絶対的価値 ――真の父母と重生摂理――
さて、これまで本稿では、真の父母の絶対的価値については、特に存在論的観点から論じてきた。しかしそのことは、救済論的(復帰摂理的)観点からも言いえるだけでなく、真の父母論を論じる上で不可欠且つ本質的問題でもある。そこでこの観点からの問題もここで簡潔に取り上げておきたいと思う。
すなわち「統一原理」では、「復帰摂理」(救いの摂理)とは、人類を本来の位置と状態に戻す摂理のことである。それは、人類が本来の位置と状態から離脱したこと、すなわち堕落したことが前提となっている。では人類の堕落とは何であったかと言えば、本来人類は神の血統を持った神の直系の子女となるべきであったが、人間始祖がサタン(天使長)と不倫な愛の関係(血縁関係)を結んだ結果、サタンの血統を持つサタンの子女となってしまった、ということである。
したがって、復帰摂理とは、本来の位置と状態に戻すことであるから、その中心的テーマは、サタンの血統を受け継いだ(原罪をもった)人類を、神の血統を受け継いだ神の子女の位置と状態に戻すこと(原罪清算)、にあると言える。そして、そのことは、神の血統を持った父と母、すなわち真の父母によって生みなおされること、つまり真の父母により血統転換=祝福されることによってのみ可能なことである――換言すれば、それは真の父だけでも真の母だけでも成されず、両者によってのみ成されるものである――。
それ故、復帰摂理的観点から見ても、真の父母という存在は、堕落した人類にとってなくてはならない存在であり、それ故また絶対的価値を持つ存在である、といえる。
ところで、非原理的集団を支持する人たちの中には、以上のような視点――〝人類の血統的堕落〟といった問題、またその解決の道としての真の父母による「血統転換」「祝福」といった天一国時代の信仰の中心的本質的問題――に対し、明確な認識を欠いているように思える人たちがいる。天一国時代の信仰の本道を行かんとする者は、このような復帰摂理の根幹的問題(血統的問題)に対しても、明確な理解と認識を持っているべきであろう。
以上で補足的な考察(論述)を終え、話を本筋にもどしたいと思う。
16 真のお母様と一つになって生きる
さて、われわれは、本稿の前半、項目「13」にいたるまでの議論で一つの結論を得た。それは結局、一口で言えば、天宙において最終的に勝利(定着)され、絶対、唯一、不変、永遠的な中心核的実体となられた真の父母様と、――したがってまた地上においてはその代表としての真のお母様と、今こそ一つとなって「天一国」建設に邁進しよう、ということであった。
そこで、最後に、上記結論を実践に移すべく、その方向性を提示するという意味で、ここに「真のお母様と一つになって生きる」というテーマを掲げ、考察することをもって本稿の締めくくりとしたい。
さて、「真のお母様と一つになって生きる」というテーマを考えるとき、筆者にとって原点となるお母様のみ言がある。それは前出のお母様を囲む特別集会(注26)でのみ言である。
――実は、筆者も恵みを得て、このツアーの一員として同集会に参加させていただいていたのであるが――、その集会でお母様は、「皆様は真のお父様を愛し慕って来ましたね?」とたずねかけられ、皆が「はい」と答えると、お母様はすかさず「では皆さんは、これまでどれだけ私にそのようにしてくれましたか」、という主旨のみ言があった。その率直なお母様のみ言は、そこにいた者たちの心に痛く響いたが、しかしそれはまた「お母様の時代」が来たことを、はっきりと自覚させられるみ言でもあったのである。
ところで、そこでの「どれだけ私にそのようにしてくれましたか」というお母様のみ言は、今日、お母様がいろいろな場で語られる「私と一つとなってほしい。そこに勝利の道があるのです」というみ言と、軸を同じくするものではある。しかしながら、そこには、日本の家庭連合の幹部や先輩家庭に対してであればこそ訴えたい、一歩踏み込んだお母様の願いが込められていたように思う。すなわち、そのみ言からは、単に「私と一つになってほしい」ということにとどまらず、われわれが真のお父様に対してそうであったのと〝同じ心情基準〟で、お母様に対してもそうあって欲しい、というお母様の切なる願いが、感じ取れるのである。しかしそれは、お母様の願いだけにとどまらず、まさしく天の父母様の願いでもあり、また真のお父様の願いでもあると言えるであろう。
なぜなら、真のお母様は御聖婚以後52年間に亘り、真のお父様と一つになって過酷な十字架の道を歩まれ、最終的に真のお父様と共に、真の父母として勝利されたからであり、また真のお父様聖和以後、「私だけが残りました」という心境で「中断なき前進」を宣言され、今尚真の父母様の代表として地上の摂理を牽引されておられるからである。否、それだけではない。より本質的な次元から言えば、真の父母様が実体的に定着されたということ、すなわち、絶対、唯一、不変、永遠的な真理的実体となられたということは、真のお父様は父なる神(神の男性性相)の、また真のお母様は母なる神(神の女性性相)の顕現者となられた、ということを意味するものである(注27)。そしてそのことは、両者(真のお父様と真のお母様)が、同等の絶対的価値を持ち、侍られるべき存在であることを意味している。なぜなら「統一原理」的観点から見れば、男性と女性は、その属性は対象的であるが、共に同価値を持っていると言えるからである。またもっと単純に言えば、真のお父様は未来永劫にわたってわれわれ全人類の共通の父(アボジ)であり、真のお母様は未来永劫にわたってわれわれ全人類の共通の母(オモニ)であるからである。
そこで、今一度、本稿冒頭の以下の真のお父様のみ言を、再度確認しておきたいと思う。
・「お母様を中心として皆さんが一体になっていかなければならない時が来ました。……お父様がいないときは、お母様のことを思わなければなりません。……先生の代わりにお母様に侍る心をもち、祈祷もそのようにするのです。今までは先生を愛してきましたが、これからはお母様を愛さなければなりません。これからはお母様の時代に入っていくことを理解して……」(「選集」265-310、1994・11・27、『絶対価値』116~117頁)。
・「大いに尊敬しなければなりません。……先生よりも、お母様をもっと重要視できる統一教会員になれば福を受けるというのです」(「選集」220-236、1991・10・19、『絶対価値』118頁)。
(注26)本稿[14の2善神の業]で言及しているが、2016年のクリスマス集会の折に持たれた特別集会。
(注27)「神様が完全な神様であれば、アダムとエバは半分の神様です。アダムも半分の神様、エバも半分の神様です」(天一国経典『天聖経』4-1-1-12)
17 「天一国」は天地人真の父母様を中心とした「心情一体世界」
では、もう一歩踏み込んで、「真のお母様と一つになって生きる」とは、どのような生き様を言うのであろうか。それは結局、「真のお母様に如何に侍るべきか」という問題であり、すなわち「真の父母様に如何に侍るべきか」という問題であって、突き詰めればそれは結局「孝」、「孝情」の問題となってくる。
では「孝」とは何か、ここに一つのヒントともいえる真のお父様のみ言がある。
・「孝子になろうとすれば、父母の心の方向と常に一致していなければなりません。孝子の道を行く人は、父母とかけ離れた行動をする人ではありません。父母が東に行けば東に行かなければならず、父母が西に行けば西に行かなければなりません。行く目的を提示したのちに、行く途中で回れ右をすれば、一緒に回れ右しなければなりません。そこに異議があってはなりません。十度行き、十度回れ右をしたとしても、また回れ右して従っていかなければなりません。反抗すれば、孝子の道理を最後まで守ることはできません」(「選集」62-32、1972・9・10、『絶対価値』44-45頁)
ここには「孝」とは何か、そのすべてが語られているわけではないが、この短い説話的み言の中に、孝に対する一つの中心的で本質的なメッセージが語られている。もちろんそれは、「ただ盲目的に親に従って行けばいいのだ」というようなことではない。――否、むしろ反対である。しっかり目を開けて従って行くべきである。どこの親もわが子が、ただ盲目的、追随的に親に従ってくれることを願ってはいない。むしろ必要に応じて質問し、確認し、意見があれば申し上げることも子としての務めというものであろう――。
ではここで何が語られ、教えられているのであろうか。すなわち、ここでは一つのぎりぎりの状況が設定されているのであり、そのような状況下に置かれた子が、どのような態度を取るかが問われているのである。何回も行ったり来たりした挙句、遂に十回目となってもうこれでなんとか終わりにして欲しいと思っているときに、また回れ右すると言う。その時、遂に頭にきて「いい加減にしてくれ、もうこんな馬鹿馬鹿しいことをやっておれるか」と尻をまくってその場を去るか、それでもなお「お父さんがそういうなら…」と言ってでもついて行くか、そこがぎりぎりの孝子になれるか否かの分かれ目になるというのである。そのような状況下では、いくら論理的に、現実的(合理的・実利的)に、時に常識的に考えても答えは出てこない。正にその場を決するのは、「情」の世界なのである。すなわち、そのような限界状況にあっても、なお子としての親に対する道理、切っても切れない愛と信頼の情を残しているかどうか、が問われているわけである。
真のお父様はよく、終わりの日(再臨時代)には「み言」と「人格(実体)」と「心情」の3つの審判があるといわれた(天一国経典『天聖経』4-3-3-9)。また「終わりの日には、宗教は心情宗教、哲学は心情哲学、主義は心情主義、思想は心情思想で各々解明されねばならない」(『御旨の道』282頁)とも語っておられる。
まず、しっかりみ言を学ぶことは、最も基本的で重要な事柄である。そしてその上で、それに相応しい人格(実体・生活)を形成することは必須の要件である。しかし、実はそれで終わるのではない。その基盤の上に立って、本然的な「心情基準」を立てることが〝最終的目標(課題)〟として、信仰者一人ひとりに残されているのである。そしてそれは、先ず縦的基準としての天の父母様と真の父母様、すなわち天地人真の父母様への「孝」の心情、「孝情」を〝しっかり〟立てることから始められなければならない――この一点が少しでも狂えば後のすべてが狂ってくる――。なぜなら、親子の関係こそ、宇宙の根本となる関係だからである(注28)。そこから横的に心情が展開され拡大されて、天地人真の父母様(実体的三位一体)を中心とした全人類一家族の心情一体世界=「天宙平和統一国」=「天一国」が形成されるのである。まさに、心情の因縁(ゆかり)で世界は生き、一つに結ばるもと(本然)の縁(『聖歌』7番)なのであり、「『孝情』の光」が世界を救うのである(『人類の涙をぬぐう平和の母』308頁参照)。
み言をよく学び、しっかりとした信仰生活をされてきた人たち(大先輩)の中でも、この〝最後〟の心情の審判、とりわけ天地人真の父母様に対する「孝情」の審判、試練を越えられず、道を踏み外してしまわれる方がおられることは、極めて残念なことである。
今世界は、コロナパンデミックから始まり、あらゆる次元で大混乱に陥っている。この世界を最終的に如何にして救うか。黙って見ているわけにはいかない。互いに知恵を出し合い、時に口角泡を飛ばし「正論」をぶつけ合うことも必要である。否、それは必須ですらある。だがしかし、互いに真剣になればなるほど、そこに激しい論理的また感情的対立が生じることも、また事実なのである。すなわち、最終的に〝主義主張〟が優先されるところ、そこには戦いの止むことがないのであって、そこに民主主義世界=兄弟主義世界の限界があるといえる。では、もしそれを越え、人類が真に恒久的な平和を享受しえる世界があるとするならば、それは家庭的原理に基づく世界(心情主義、家庭主義、父母主義、神主義、頭翼思想)以外にはありえない――ここに今日「家庭連合」が存在する理由がある――。すなわち、その世界は、〝父母〟を中心として、〝最終的に〟力でもなく、主義主張でもなく、心情(真の愛)を中心として一つになれる世界なのである。
であるとするならば、まさしくわれわれが目指している天の父母様と勝利された真の父母様(天地人真の父母様)を中心とする全人類一家族の世界=「天一国」こそ、その世界といえるであろう。
そして、そこに至る最初の一歩は、今尚、われわれと共にこの地上に居られ、真の父母様を代表して歩まれる真のお母様と一つになっていくところから始まるのである。
(注28)「この宇宙の究極的な真理の問題を前にして……神秘的な境地に入って、人間が探し求めるべき宇宙の最高の真理が何かということを打診したとき、その時に得た答えが、『父子関係』という言葉なのです」(天一国経典『天聖経』4-1-1-17)
完
(2023年3月吉日)
<参考文献>
天一国経典『天聖経』世界平和統一家庭連合
『真の父母経』世界平和統一家庭連合
『文鮮明先生の日本語による御言葉集8』光言社
『御旨の道』世界平和統一家庭連合
『人類の涙をぬぐう平和の母』光言社
『原理講論』世界平和統一家庭連合
『真の父母の絶対価値と氏族的メシヤの道』光言社
『「原理講論」に対する補足説明』太田朝久
『真のお母様、感謝します』光言社
『世界家庭』世界平和統一家庭連合月刊誌・光言社
『組織神学』ヘンリー・シーセン・聖書図書刊行会
『基督教全史』E・ケァンズ・聖書図書刊行会
『キリスト教の歴史』小田垣雅也・講談社
『現代キリスト教神学入門』W・E・ホーダーン・日本基督教団出版局
『20世紀のプロテスタント神学(上・下)』H・ツァールント・新教出版社
『現代神学の最前線』栗林輝夫・新教出版社
『キリスト教大事典』教文館
『サンダー・シング全集』金井為一郎著訳・基督教文書伝道会
『エマニュエル・スウェデンボルグの霊界Ⅱ』E.スウェデンボルグ著、今村光一抄訳・編集、中央アート出版社。